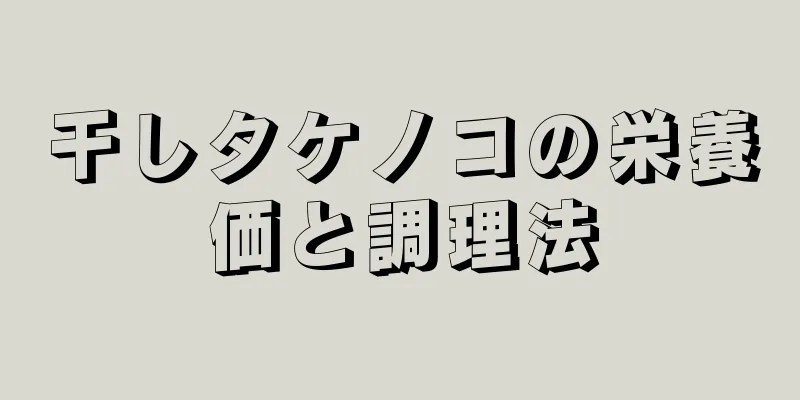マスタード塊茎の漬け方 マスタード塊茎の漬け方

|
私たちは日常生活で、からし芋の漬物を食べるのが大好きですが、市場で購入したからし芋の漬物には、通常、化学物質が添加されています。長期間摂取すると、体にさまざまな程度の害を引き起こします。今日、編集者は、健康的なからし芋の漬物を自分で作る方法を紹介します。からし芋の漬物が特に好きなら、自分で詳しく調べてみるのもよいでしょう。自分で作るのもとても良いことです。 マスタードの漬物の準備コールラビ、塩、五香粉、唐辛子 マスタード塊茎の漬け方1. 自宅でコールラビを栽培する場合は、切り取って地面に置いて1〜2日間冷やし、ナイフで根を切り落としてから、たっぷりの水で洗ってください。市場で購入した場合は、ナイフで根を切り落としてから、たっぷりの水で洗ってください。 2. コールラビを洗い、包丁で仏の手の形に切り、塩で水分を取り除きます。マリネには通常4〜5日かかります。 3 漬け込んだコールラビを取り出し、清潔な場所に置いて乾燥させます。一般的には、70% 乾いたら手でこすると柔らかくなり、味が良くなります。 4. 擦ったコールラビを容器に戻し、風味を良くするために3日間ほど漬け込み、取り出して天日で乾燥させます。 5. 日光が当たる場所であれば、1~2日乾燥させてから、乾燥したコールラビを瓶に入れ、五香粉と唐辛子を加え、均一にかき混ぜてから、蓋を閉めて瓶の溝に適量の水を加えます。 6. 数日漬けておけば食べられます。マスタード塊茎の漬け方のヒント1. 柔らかいコールラビや古いコールラビを選ぶこともできますが、味は異なります。 2. 他の調味料を加えると味がさらに良くなります。 3. 瓶は風通しがよく、乾燥した涼しい場所に置くのが最適です。 4. 蓋を開けて取り出し終わったら、必ずしっかりと密封してください。そうしないと空気が漏れてしまいます。 |
<<: 新鮮なマスタード塊茎の作り方と新鮮なマスタード塊茎を使った肉炒めの作り方
推薦する
ドリアンが腐るとどうなるのでしょうか? ドリアンが腐るとどんな危険があるのでしょうか?
ドリアンは多くの人に好まれる熱帯フルーツです。独特の香りがありますが、栄養が豊富で、体を養い、新陳代...
妊婦が牛乳を飲むとどんなメリットがありますか?
毎日牛乳を飲むのは、多くの妊婦の習慣です。牛乳を飲むことは妊婦にとって多くの利点があります。大人にと...
ウロコゼミの鉄の効能と機能
鱗状枯れゼアミアはゼアミア属の植物です。ヒメウナギの原産地はメキシコです。雌雄異株の植物です。一般的...
ヤマモモの洗い方、ヤマモモの掃除方法
ベイベリーをきれいに洗うにはどうすればいいですか?多くの友人が答えを知りたがっていると思います。以下...
新鮮なヘチマ苗の効能と機能
新鮮なヘチマは誰もが食べたことがあるでしょう。夏の定番料理ですが、新鮮なヘチマの苗を見たことがありま...
桜の植え付け条件と地域の気温要件
チェリーの紹介チェリーは、バラ科およびサクラ属のいくつかの植物の総称です。中国では桜の栽培は長い歴史...
生のニンニクを食べるとどんなメリットがありますか? 生のニンニクを食べるとどんなメリットと効果がありますか?
生ニンニクは新鮮なニンニクです。ニンニクは加工されていない野菜の一種で、辛くてニンニク独特の風味があ...
ごぼうを収穫するのに最適な時期はいつですか?植え付けと収穫の時期
ごぼうの収穫時期秋ゴボウは、幼虫による被害期間を避けるため、6月末までに収穫する必要があります。春ご...
宝石花の効能と機能 宝石花の薬効
ジェムフラワーは多年生の多肉植物で、蓮に似ています。一年中緑色で、とても美しく魅力的です。鉢植えにし...
大根の食べ方とタブー
大根はとても一般的な野菜です。栄養価を最大限に得るには、どのように食べればよいでしょうか?ぜひここで...
ハミメロン、ユリ、赤身肉のスープのレシピと効能
ハミメロン、ユリ、赤身肉のスープについては、言いたいことがたくさんあるので、簡単にまとめたいと思いま...
豆腐を植えるのに最適な月は何月ですか?
豆腐を植える時期豆腐菜は通常、春か秋に植えられます。通常、豆腐菜は春の4月に植えるのが最適ですが、こ...
琉璃翠ローズの長所と短所
リウリクイ ローズはケニア原産の切り花品種です。背の高いカップ型の花が咲きます。黄色と緑の色が特徴で...
ニガヨモギの効能、効果、禁忌
グナファリウムは一年生または二年生の野生草本です。この植物は成長しても高さが50cmを超えません。茎...
かぼちゃとあさりのお粥
皆さんのほとんどは、柔らかいカボチャとアサリの693粥をめったに食べないと思います。この粥についての...