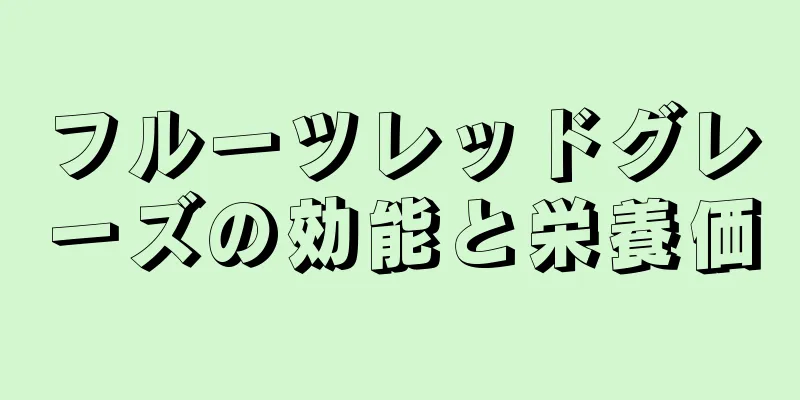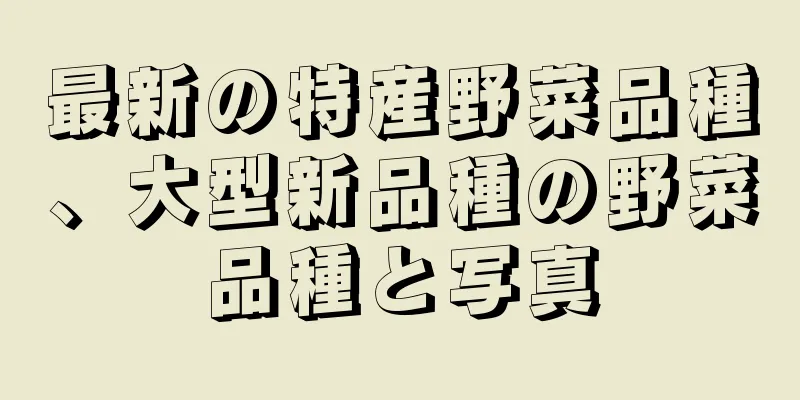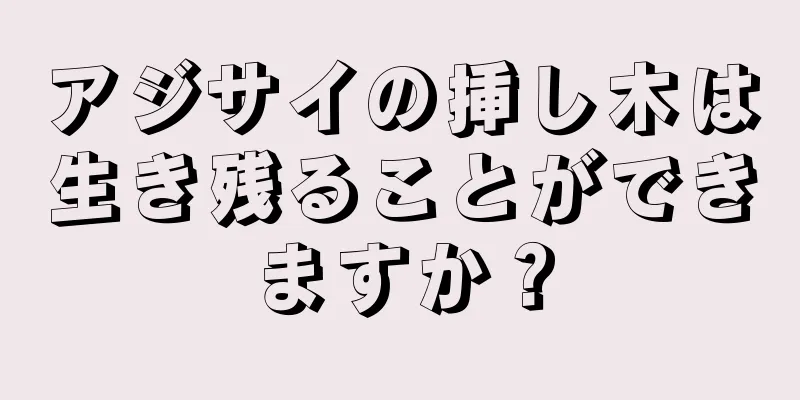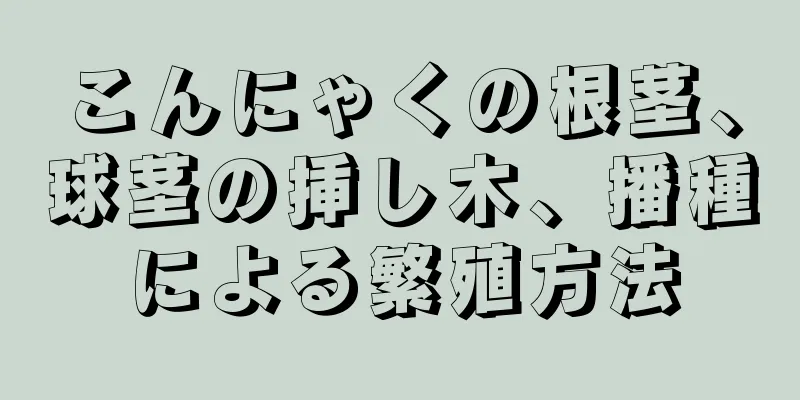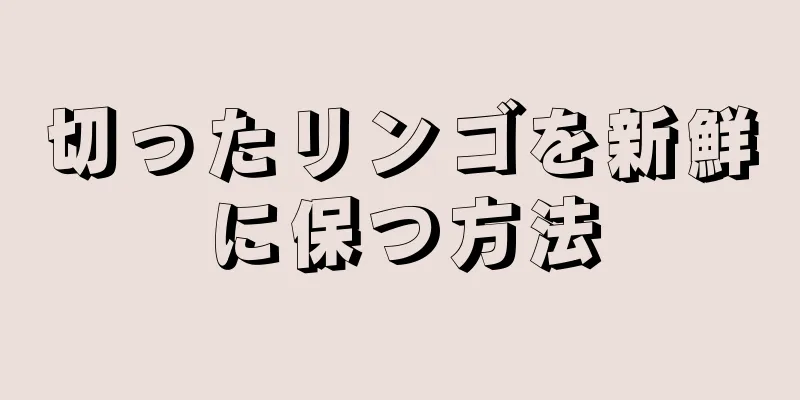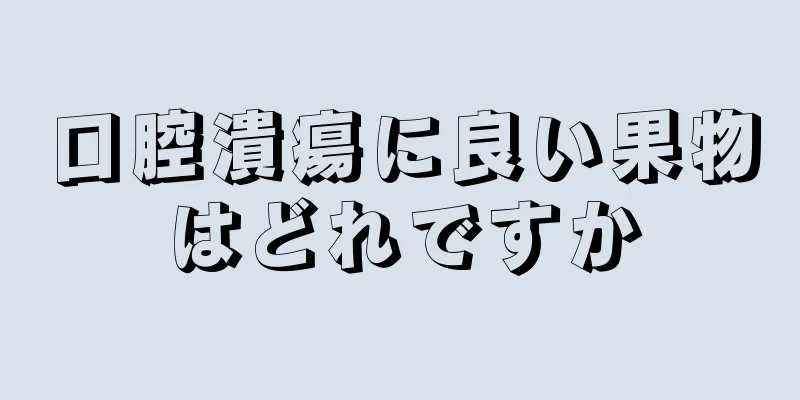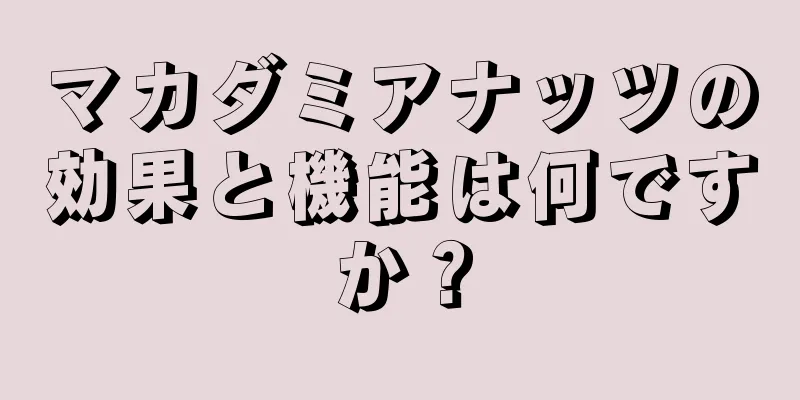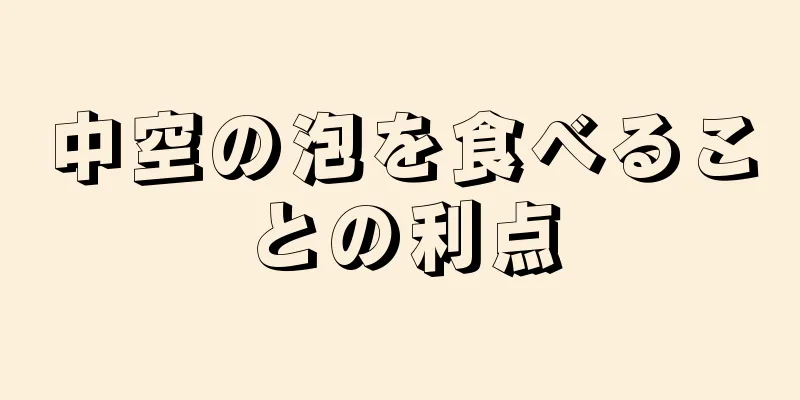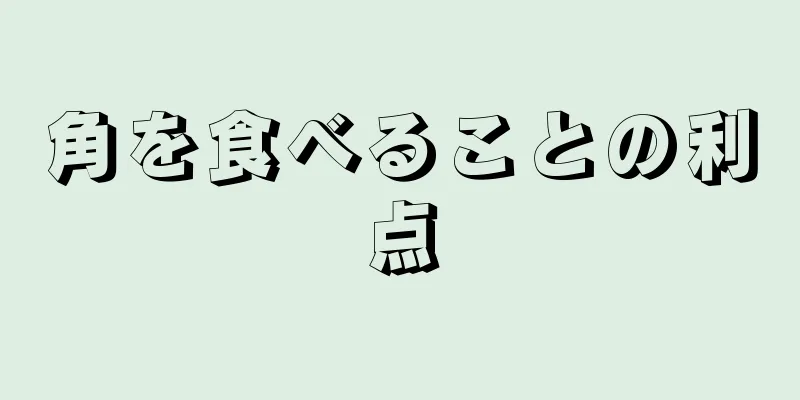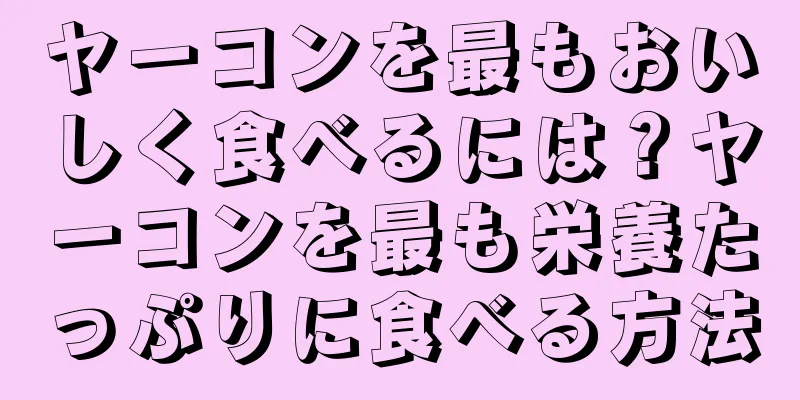食後どれくらい経ってから果物を食べても大丈夫ですか?食後すぐに果物を食べることのデメリットは何ですか?
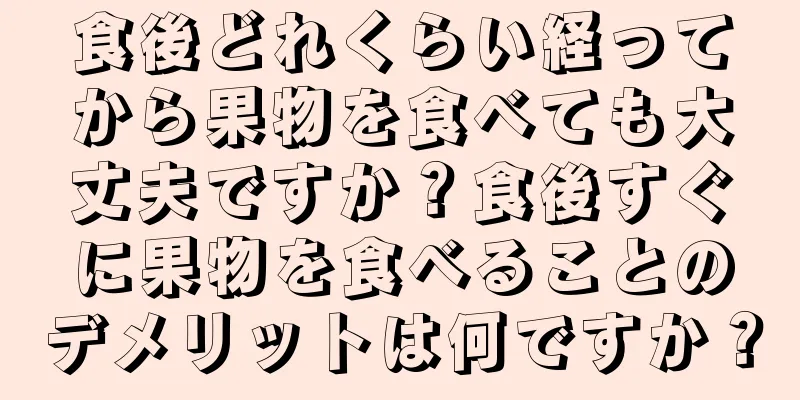
|
果物は生活に欠かせない食材であり、食後に果物を食べるのが好きな人も多くいます。しかし、食後すぐに果物を食べると健康に害を及ぼす恐れがあります。では、食後どれくらい経ったら果物を食べられるのでしょうか?食後すぐに果物を食べることのデメリットは何ですか?これらの問題についてさらに詳しく知りたい場合は、私をフォローしてご覧ください。 食後どれくらい経ってから果物を食べても大丈夫ですか?食後すぐに果物を食べることのデメリットは何ですか?1. 食後どれくらい経ったら果物を食べられますか? 通常、果物を食べるのに最適な時間は食後2~3時間後です。ただし、食事中に高タンパク質食品をたくさん食べる場合は、果物を食べる時間を長くする必要があります。これにより、体はタンパク質をよりよく吸収して利用し、果物の成分によってタンパク質が破壊されるのを防ぐことができます。また、腹部膨満や便秘などの悪影響の発生を減らすこともできます。 2. 食後すぐに果物を食べると、膨満感や便秘を引き起こす可能性がある 食後すぐに果物を食べると、果物に含まれる天然の単糖類が小腸や胃に蓄積し、胃腸の働きが遅くなります。ひどい場合には、腹部の膨満感を引き起こすこともあります。したがって、食後すぐに果物を食べるべきではありません。さもないと、便秘、膨満感、その他の悪影響を引き起こします。 3. 食後すぐに果物を食べると、栄養素の吸収に影響が出る ほとんどの果物には、大量のビタミンCといくつかの天然フルーツ酸が含まれています。これらの物質は、他の食品のタンパク質と反応して消化できない物質を形成します。また、微量元素である銅の体内吸収にも影響します。したがって、食後すぐに果物を食べるのは体に良くありません。体内のタンパク質の吸収と利用が簡単に低下する可能性があります。時間が経つにつれて、銅欠乏によるさまざまな病気も発症します。 |
<<: バナナの皮を煮た水を飲むとどんな効果があるのでしょうか?
>>: ナツメを食べ過ぎるとどうなる?ナツメを食べ過ぎるデメリット
推薦する
カスミソウの種の保存方法
カスミソウの種子の紹介カスミソウには種子があり、果実の中で成長して8月から9月に成熟します。種子は非...
広西チワン族自治区でキウイフルーツは栽培できますか?
広西チワン族自治区でキウイフルーツは栽培できますか?広西チワン族自治区はキウイフルーツの栽培に非常に...
グレープフルーツを食べるとどんなメリットがありますか? グレープフルーツを食べるとどんなメリットと効果がありますか?
毎年秋になると、市場にはグレープフルーツが大量に出回ります。果物市場で大きなグレープフルーツを次々に...
大根粥の効能とダイエット効果
大根を食べるのは好きですか?生活の中で最も一般的な野菜の一つであり、栄養が豊富です。摂取すると人間に...
アスパラガスシダに最適な肥料は何ですか?
アスパラガスの肥料アスパラガスシダは肥料を好みます。成長過程においては、有機肥料、固形肥料、分解肥料...
血液を補給する食べ物は何ですか?
貧血や血液供給不足は身体に悪影響を及ぼす可能性があります。特に女性の友人は特殊な体質のため、男性より...
赤乳ブドウの効能と機能
レッドミルクグレープを食べたことがありますか?その効果と機能をご存知ですか?赤乳ぶどうは、ユーラシア...
アルファルファの生育環境条件と特徴
アルファルファの生育環境条件と要件アルファルファは湿気のある環境を好み、一般的に畑、道端、荒野、また...
ヒスイの木の花を咲かせる育て方
ヒスイの花セダムは通常、夏と秋に開花します。開花期間が非常に長いです。夏と秋に咲き、100日以上咲き...
野生ツツジの栽培方法と注意点
野生ツツジは昔から人々に愛されている観賞用花です。人々は自宅でも野生ツツジを育てていますが、育て方が...
絞りたてのリンゴジュースに水を加える必要はありますか?リンゴジュースを絞る際のヒントと注意事項
日曜日に家で絞りたてのリンゴジュースを作りたかったのですが、作るときに水を加えるべきかどうかわかりま...
カンナの種を植える方法
カンナの種が成熟したら、種を取り出し、見た目が良く、より充実したものを選び、水で洗い、風通しの良い場...
白砂糖蒸し卵の効能と機能
白砂糖をかけた蒸し卵を食べたことがありますか?具体的な効果は何かご存知ですか?砂糖入り蒸し卵、そうで...
ユシュは太陽が好きですか?
ユシュは太陽が好きセダムは太陽を好み、太陽を愛する植物です。光条件が良好で、暖かく乾燥した地域での栽...
干しヒトデをワインに浸す方法 干しヒトデをワインに浸す効果
多くの人の目には、ヒトデは一種の食用生鮮食品です。ヒトデを食べると豊富な栄養素を吸収できることは知っ...