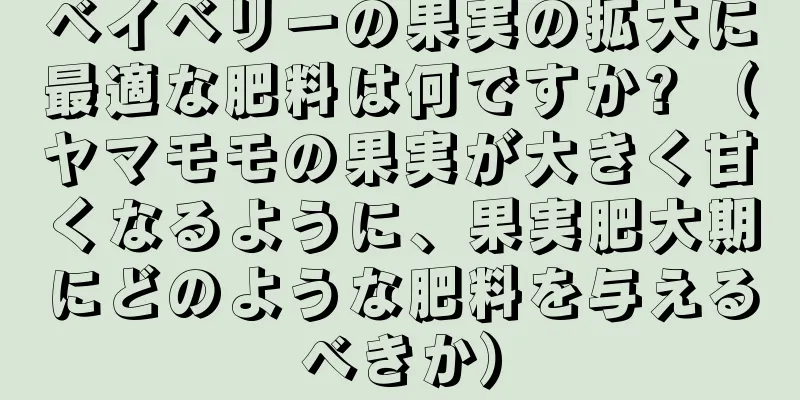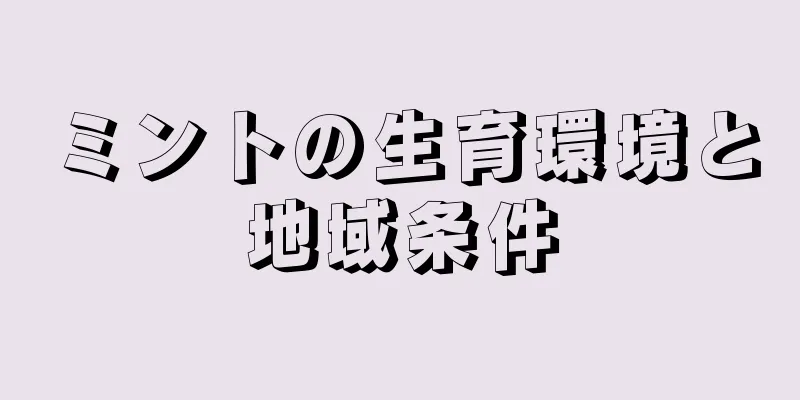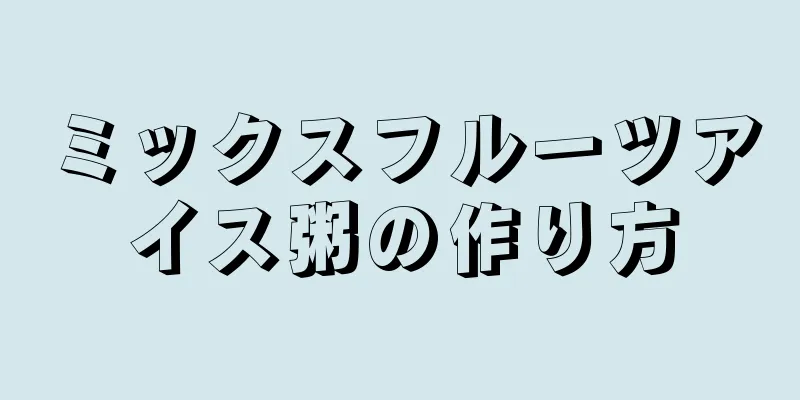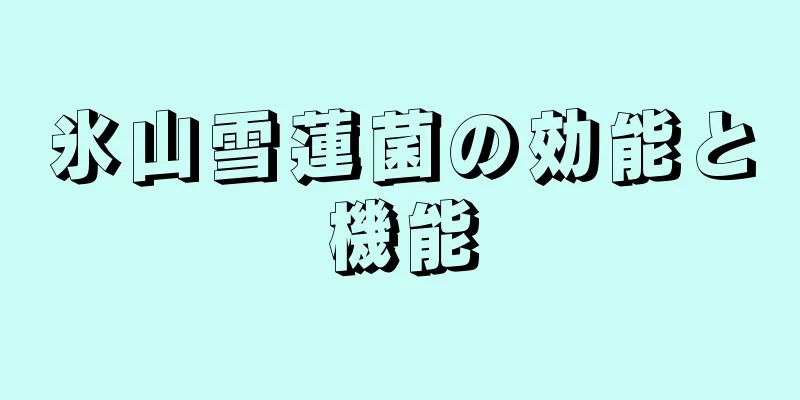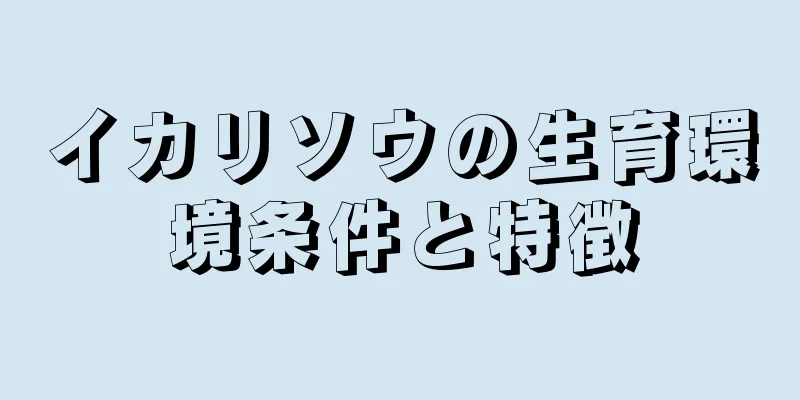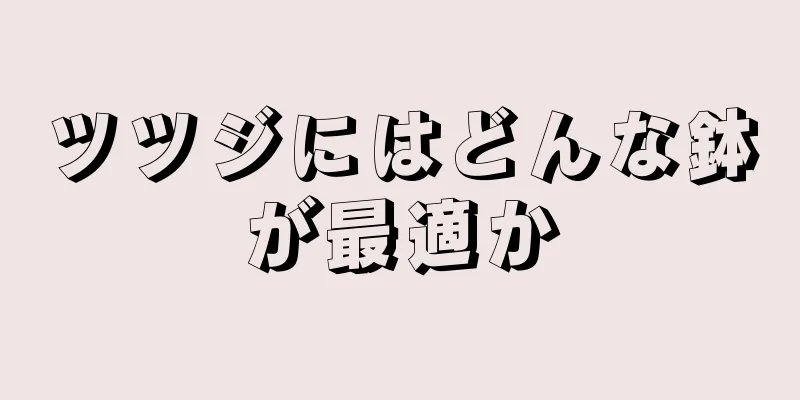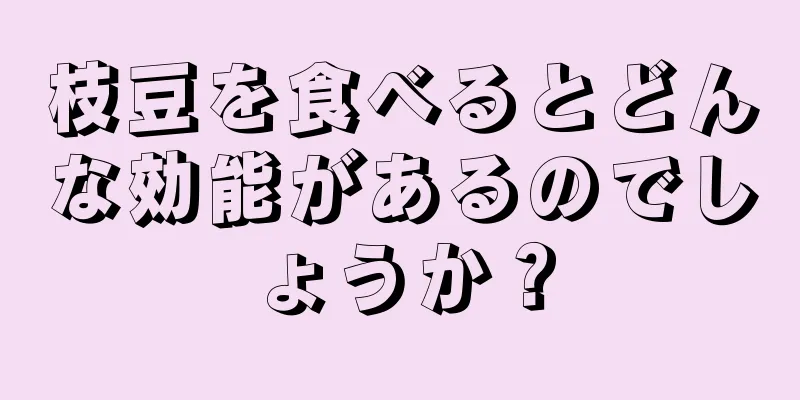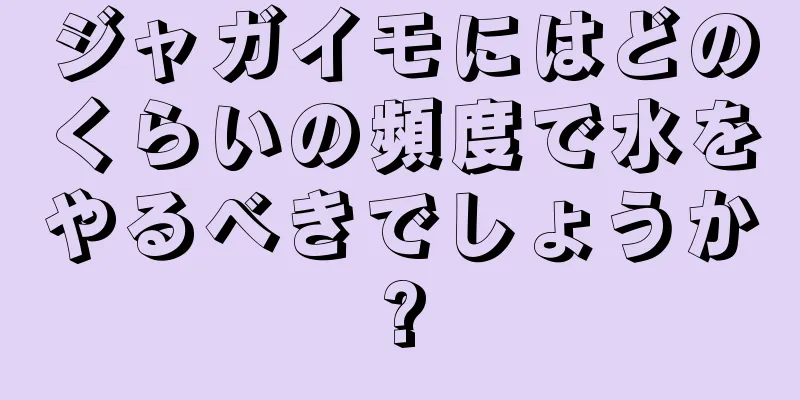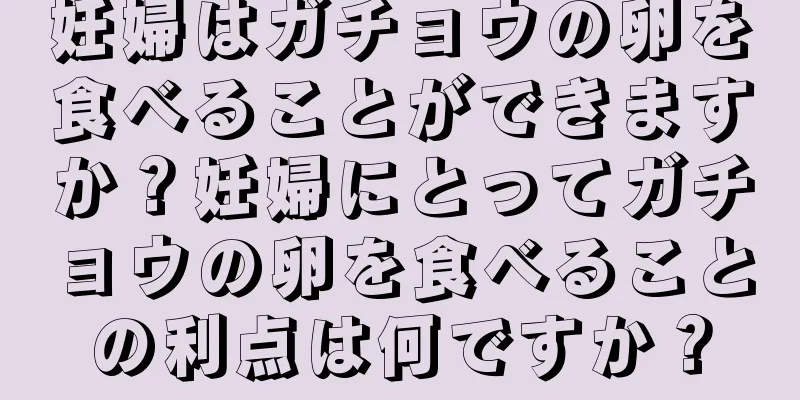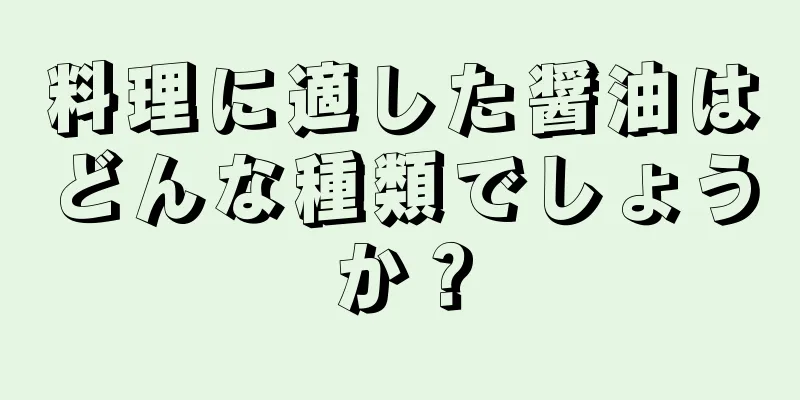漬けピーマンを食べることの利点と欠点
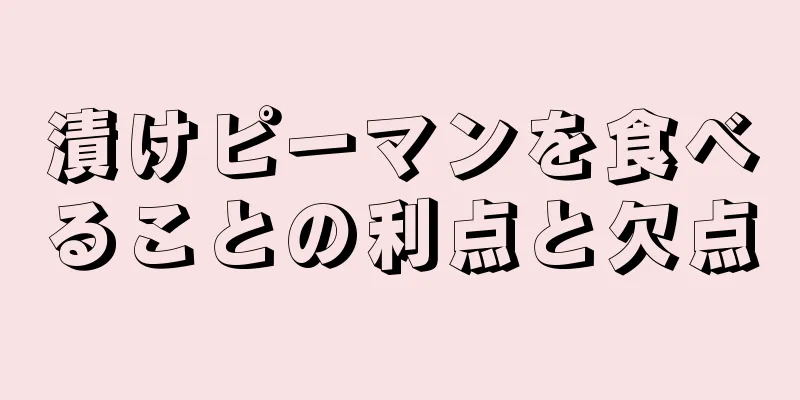
|
ピクルスにした唐辛子の鶏足は、多くの人に人気のスナックです。新鮮な鶏足にピクルスにした唐辛子やその他の調味料を加えて作ります。市販されている完成品は、ほとんどが真空パックされています。香りがよく、肉が柔らかく、ほんのりスパイシーな風味があります。ご飯と一緒に食べても、ワインと一緒に食べてもおいしいです。では、ピクルスにした唐辛子入り鶏足を食べることの利点と欠点は何でしょうか?知りたいなら、私と一緒に行ってください。 漬けピーマンを食べることの利点と欠点1. 漬けた唐辛子の鶏足を食べると肌に栄養を与えることができる 漬け鶏足には、コラーゲンタンパク質とさまざまなビタミンやアミノ酸が豊富に含まれており、これらの物質は人間の皮膚細胞に直接作用し、皮膚細胞の再生と新陳代謝を促進します。定期的に摂取すると、肌に栄養を与え、肌をきめ細かく滑らかで弾力のあるものにすることができます。 2. 漬け唐辛子鶏足を食べると心臓が守られる 鶏足の酢漬けを食べると、心臓に良い保護効果があります。鶏足の酢漬けには脂肪酸が含まれており、脂溶性ビタミンの体内吸収を促進し、体内のナトリウムの排泄を促進し、心臓機能を改善し、心血管疾患や脳血管疾患の発生を減らすことができます。また、鶏足の酢漬けを多く食べると、カルシウム、亜鉛、銅などの微量元素も補給でき、体の新陳代謝を促進し、人間の体力を向上させることができます。 3. ピクルス漬けの鶏足を食べることのデメリット 鶏足の漬物を適度に食べることに害はありませんが、ほとんどの鶏足の漬物には加工中に漂白剤が加えられており、人体に入ると人体組織にダメージを与えます。喘息、肺気腫、慢性気管支炎の人は、鶏足の漬物を長期摂取すると、身体に不快感を覚えることがあります。そのため、これらの特別なグループの人は鶏足の漬物を適度に食べる必要があります。 |
推薦する
砂糖ニンニクの漬け方 自宅で砂糖ニンニクを漬ける方法
ニンニクは辛味があり、生で食べると受け付けない人も多いので、家庭で塩ニンニクや砂糖ニンニクを作るのが...
レッドカンファレンスナシの植え付け条件と気候要件
レッドペアの紹介赤い梨はとても美味しい果物です。果実の表面は青みがかった赤色で、小さなひょうたんによ...
干し大根を素早く漬ける方法
干し大根は、冬の食卓で最もよく食べられるおかずです。美味しくて食欲をそそるだけでなく、気を整えて消化...
バイカラージャスミンの育て方 バイカラージャスミンを育てる際の注意点
バイカラージャスミンは、多くの人が好む鉢植えの植物です。誰もが、環境を鑑賞し、美しくするために、室内...
剪定された雲竹の枝は生き残ることができるでしょうか?切った枝をどうやって増やすのですか?
剪定された雲竹の枝は生き残ることができるでしょうか?雲竹は挿し木で育てることもできますが、細い枝は生...
ピタヤの花の効能と機能
ドラゴンフルーツは誰もが食べたことがあるでしょう。一般的な熱帯果物ですが、この植物についてご存知です...
苔を使って多肉植物を育てることはできますか?
苔を使って多肉植物を育てることはできますか?苔は多肉植物を育てるのに使えます。純粋に天然の植栽資材で...
大根とラム肉の煮込みの作り方
ラム肉を大根と一緒に煮込んだ料理は栄養価が高く、寒い冬の滋養強壮に最適だと聞きました。食べたことがあ...
花釣鶏とは?花釣鶏の作り方
南に行ったことがある友達は、おいしい花釣鶏を食べたことがあるかもしれませんが、花釣鶏とはどんな料理で...
野生のコプリヌス・コマツスの効能と機能。野生のコプリヌス・コマツスの準備手順。
野生のヒトヨタケの学名はCoprinus comatusです。鶏の脚のような外観と、細切りの鶏肉に似...
種あり君前子と種なし君前子の違い
君千子は人間が食べられる植物の果実で、黒ナツメやミルクナツメとも呼ばれ、カキ科の植物の一種で、主に中...
ザクロの皮を食べることのメリット
皆さんもザクロを食べたことがあると思います。お聞きしたいのは、ザクロを食べるとき、ザクロの皮は全部捨...
黒トリュフとは?黒トリュフの効果や機能は何ですか?
黒トリュフって何だかご存知ですか?黒トリュフの効果や働きをご存知ですか?黒トリュフは貴重な野生の食用...
干しナスの作り方 干しナスの食べ方
今日は干しナスについての一般的な知識とその食べ方をご紹介します。干しナスの紹介干しナスは江西省北東部...
幸運の竹に水をやる方法
幸運の竹の水やりのポイント幸運竹はリュウゼツラン科ドラセナ属の植物です。一般的に、水やりのタイミング...