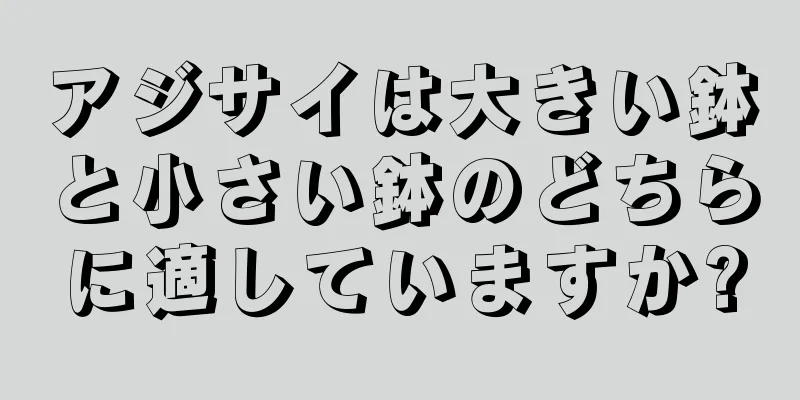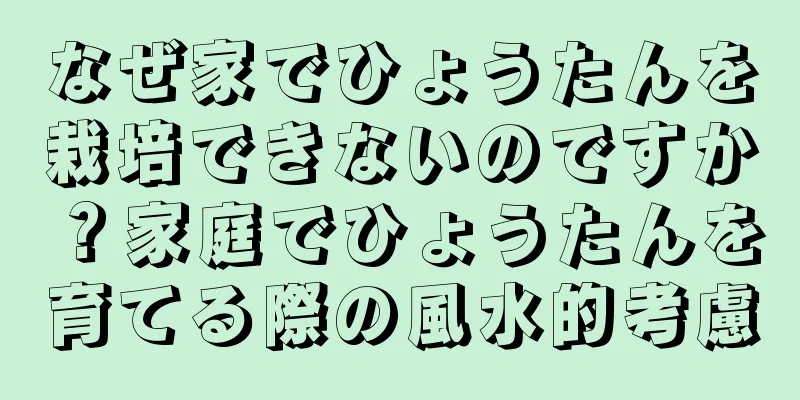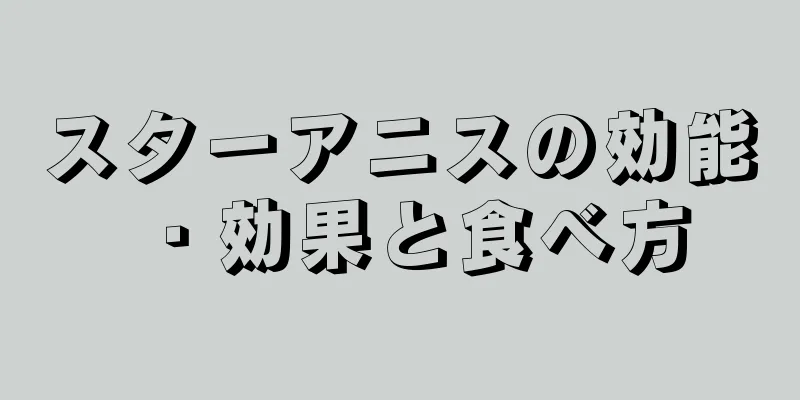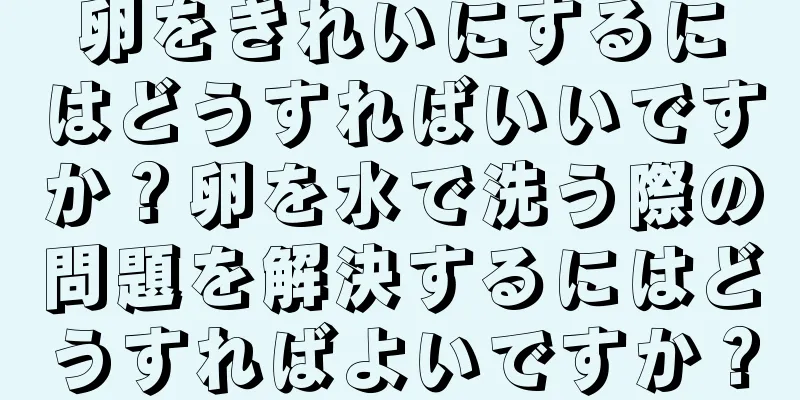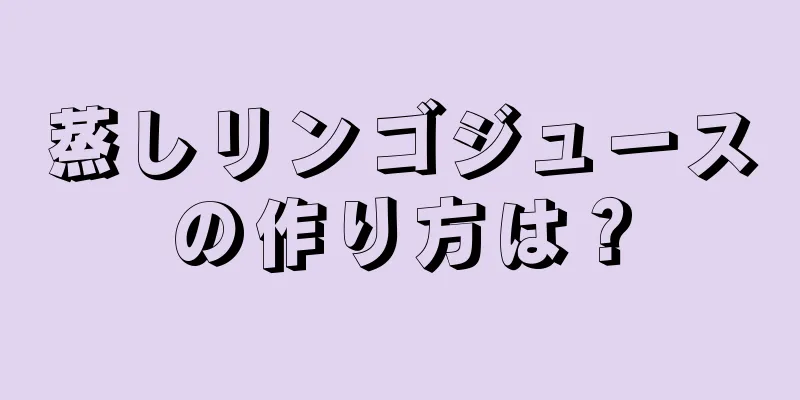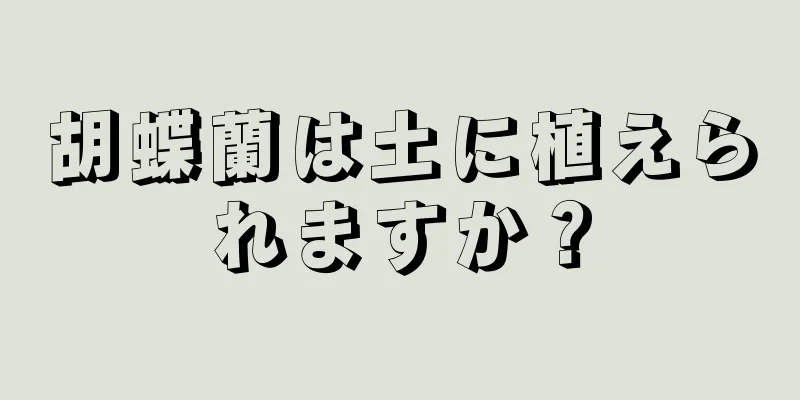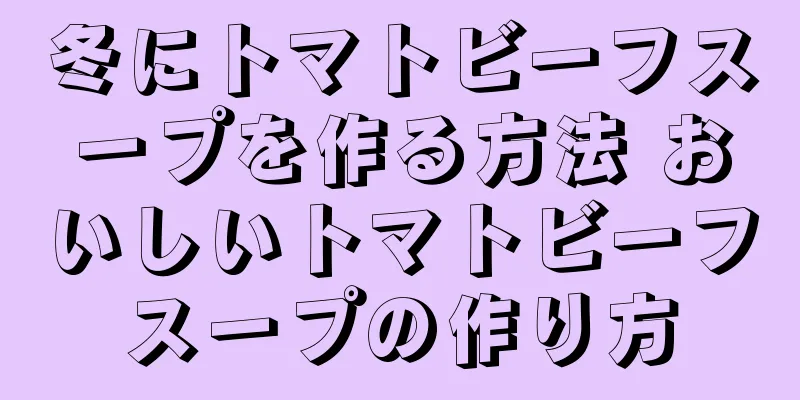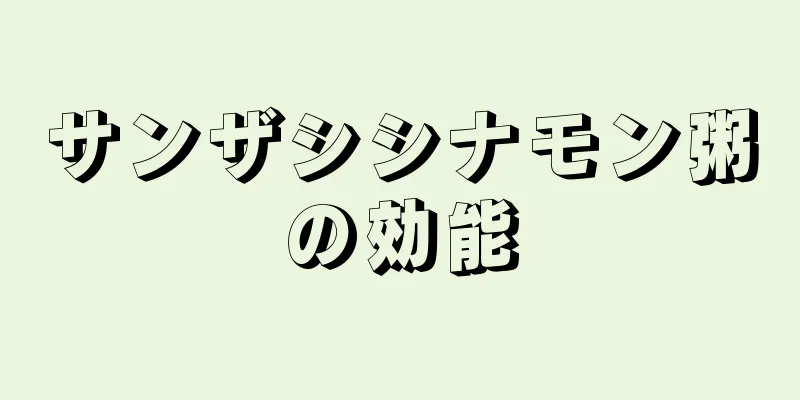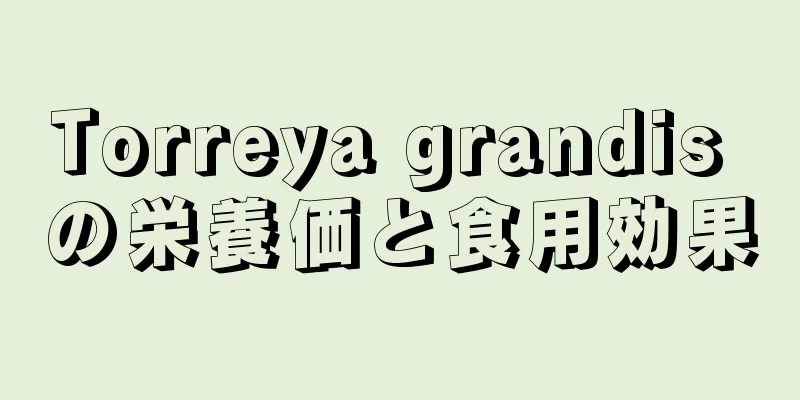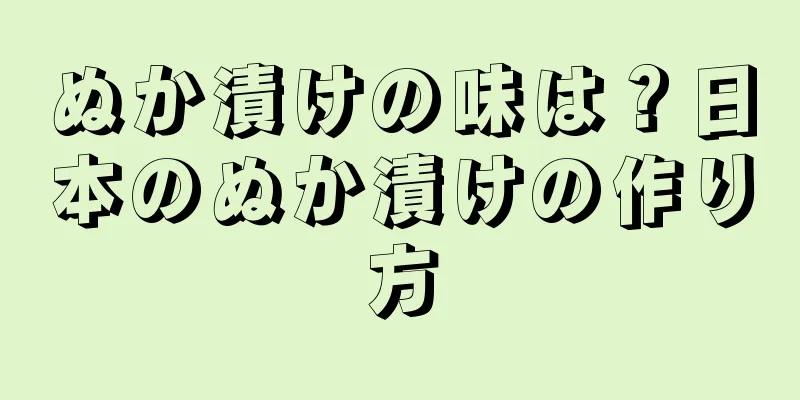ローヤルゼリーの食べ方 ローヤルゼリーの一般的な食べ方
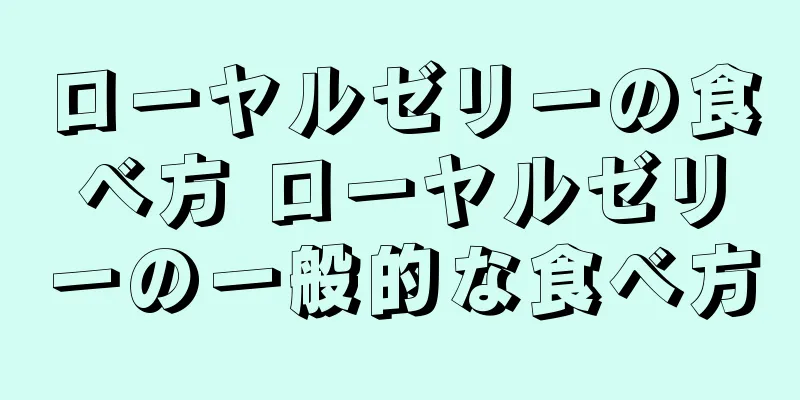
|
ローヤルゼリーは最高品質の蜂製品であり、優れた栄養価を持つ強壮剤です。主に乳白色または淡黄色の濃厚なペーストです。ただ、生ローヤルゼリーについて日常生活ではあまり知られておらず、どのように食べたらよいのかわからない人も多いのです。実はローヤルゼリーの摂取方法はたくさんあります。一般的な摂取方法は後ほど書きます。ローヤルゼリーを食べたい友人は事前に知っておきましょう。 ローヤルゼリーの食べ方 ローヤルゼリーの一般的な食べ方1. ローヤルゼリーは経口摂取が最適 ローヤルゼリーを摂取する最も一般的な方法は、舌下摂取です。つまり、適量のローヤルゼリーを口に入れ、舌の下に押し付けてゆっくりと溶かしてから飲み込み、最後に少量の温水を飲みます。ここで注意したいのは、ローヤルゼリーは熱に弱いため、熱湯で摂取してはいけないということです。 2. ローヤルゼリーはハチミツと一緒に摂取できる 生のローヤルゼリーを食べたことがある人なら誰でも知っているように、ローヤルゼリーの味は魅力的ではなく、多くの人がそれを受け入れられません。このとき、ローヤルゼリーと蜂蜜を1対2の割合で混ぜ、混ぜた後に直接摂取することができます。さらに、ローヤルゼリーを蜂蜜に加えると、ローヤルゼリーの保存期間も延長されます。 3. ローヤルゼリーは凍結乾燥粉末に加工できる ローヤルゼリーは賞味期限が非常に短い健康食品です。生のローヤルゼリーを購入すると、自宅ですぐに劣化してしまいます。そのため、多くの人がそれを凍結乾燥粉末に加工し、カプセルに入れています。これにより、ローヤルゼリーの賞味期限が延びるだけでなく、摂取も便利になります。このローヤルゼリー凍結乾燥粉末を摂取するときは、温水で直接摂取できます。ローヤルゼリーは食事の約1時間前に摂取するのに適しています。食後に摂取すると、ローヤルゼリーに含まれる栄養素が体に吸収されにくくなります。 |
<<: コーヒーを飲むのは良いことでしょうか?コーヒーを飲んではいけない人は誰でしょうか?
推薦する
女性用美容粥の材料と手順
冬が近づいており、人々は温かいお粥を飲みたくなります。お粥の中には、特に女性に適したものがあります。...
レモネードの作り方 レモネードの正しい作り方
レモネードは多くの冷たい飲み物の店の主力商品であり、多くの子供や若者にも人気があります。しかし、市場...
バラと野バラの違いバラの効能と機能
バラと野バラはどちらも私たちの生活の中で一般的な観賞植物であり、鮮やかな色、長い開花期間、高い観賞価...
乾燥野菜と塩豚骨粥の作り方
干し野菜と塩豚骨粥の作り方は実はとても簡単です。以下に詳しくご紹介しましょう。乾燥野菜と塩豚骨のお粥...
広東の自家製米酢の作り方
広東省では、各家庭で米酢を醸造する習慣があります。地元の人が醸造した米酢は殺菌や消毒に使用でき、食べ...
ダイダイ花の効能と機能、そしてダイダイ花使用の禁忌
アスターの花は美しい観賞用植物です。その花は見た目が美しく、香りが魅力的であるだけでなく、薬としても...
キノコとアスパラガスのお粥
キノコとアスパラガスのお粥についての知識をまだ覚えていますか?覚えていない方は、以下の紹介文を読んで...
野生ニラとチャイブの違い
ヤマネギは山ネギとも呼ばれ、主に野生で育つ野生植物で、人間が食べることができます。しかし、多くの人は...
トマトジュースの効能と機能
トマトは日常生活で最も人気のある果物や野菜の1つです。皮をむいてそのまま食べたり、砂糖に浸したりする...
リプタロイモの食べ方 リプタロイモの調理方法
リプタロイモは最高級のタロイモです。リプ香るタロイモとも呼ばれています。柔らかくて粘り気のある食感と...
女性は老化を防ぐためにキウイフルーツを定期的に食べることができますか?
女性はキウイフルーツを定期的に食べることで老化防止に役立つのでしょうか?多くの女性の友人がこの件につ...
ブドウの正しい洗い方 ブドウを最もきれいに洗う方法
ブドウは甘くてジューシーで栄養価が高く、美味しい果物です。ブドウが好きな人は多いですが、食べるときに...
赤い花の玉にはたっぷりと水をあげる必要がありますか?どのくらいの頻度で水をあげればよいでしょうか?
紅花玉の水やりは徹底していますか?紅花玉は比較的干ばつ耐性が強く、多くの水を必要としないので、頻繁に...
アンジェリカとレッドデーツチキンスープの役割と効能
多くの人が「当帰と紅棗のチキンスープ」について聞いたことがあり、それが優れた滋養効果を持つことも知っ...
水に浸したゴーヤを飲むとどんな効果があるのでしょうか?水に浸したゴーヤの作り方
ゴーヤは夏に人々の食卓によく登場し、生活で最も人気のある食材です。苦味が強いですが、熱を取り除いて毒...