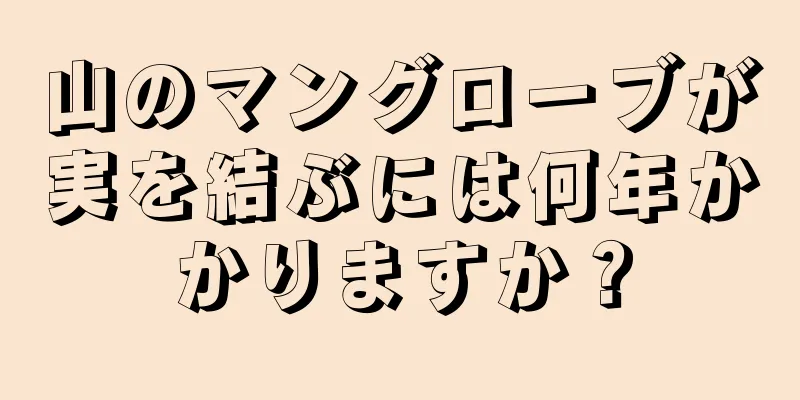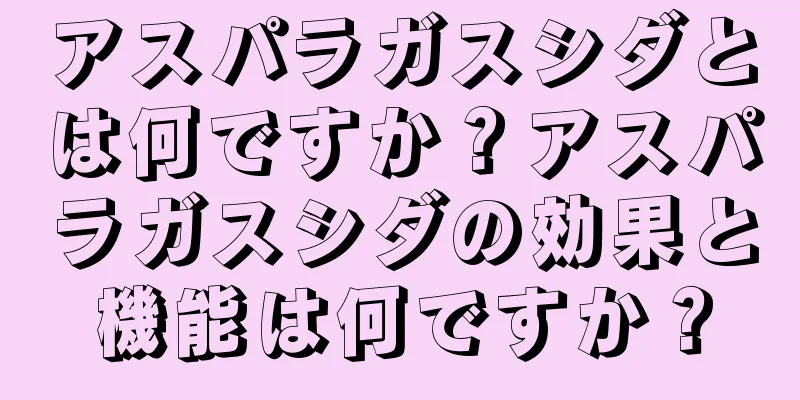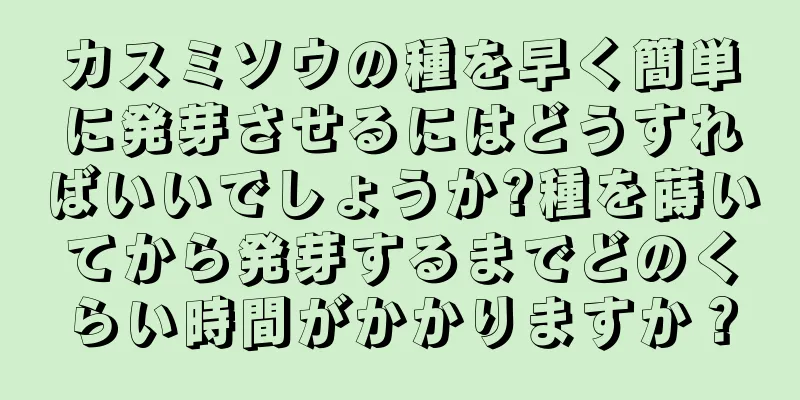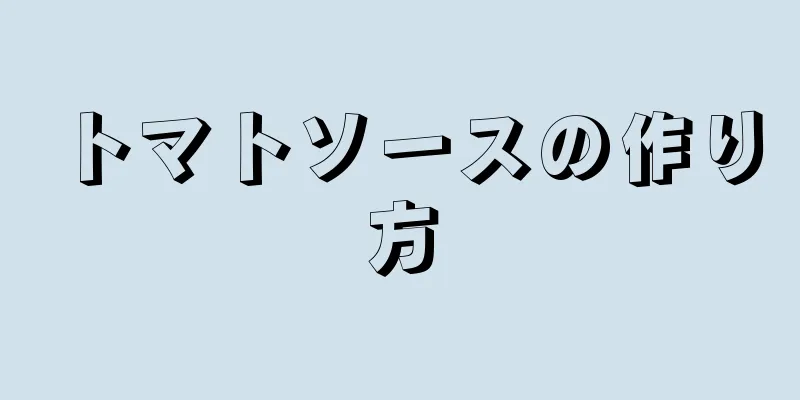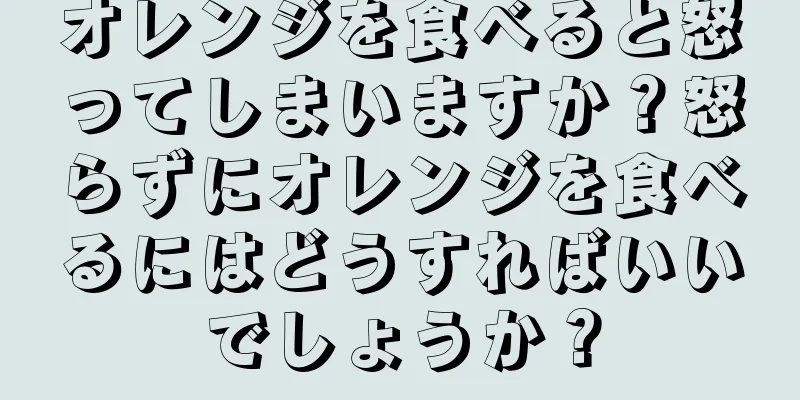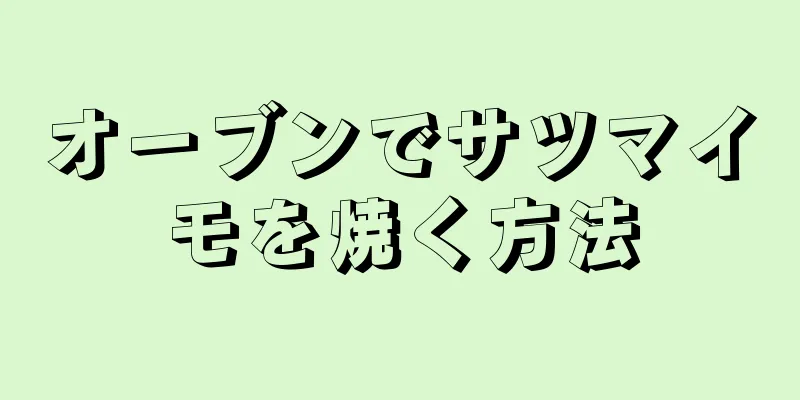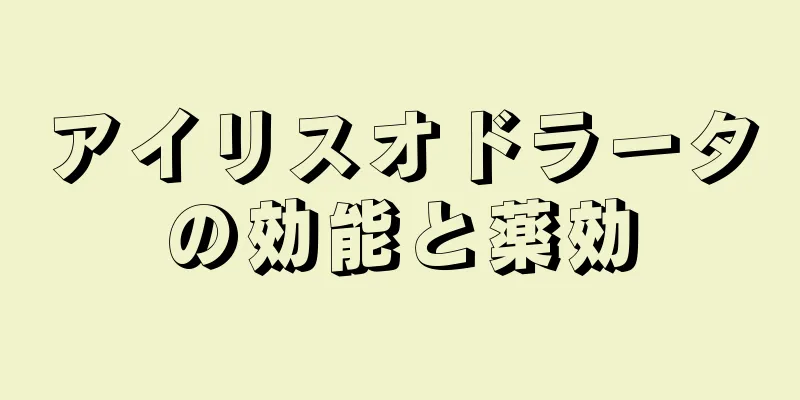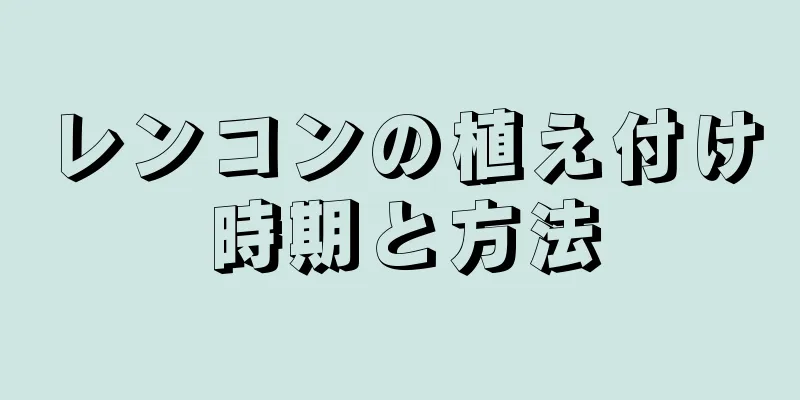カッピングは有用ですか?カッピングの利点と欠点は何ですか?
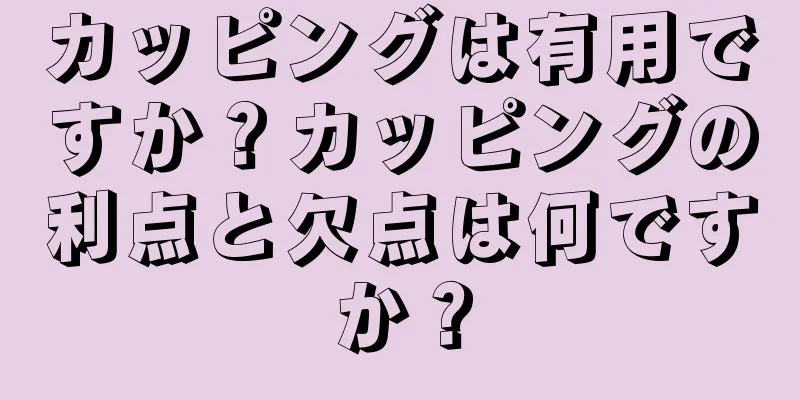
|
カッピングは近年非常に人気が高まっています。病気の治療に使われることもあれば、減量に使われることもあります。カッピングは中国医学の伝統的な理学療法ですが、日常生活で使用する場合、人体に対してメリットとデメリットの両方があります。使用する前に、身体への悪影響を避けるために、カッピングについて十分に理解する必要があります。 カッピングの利点1. 痛みや疲労を和らげる カッピングは通常、痛みや疲労を和らげることができます。生活の中で、筋肉が緊張状態にあると、局所的な血流が減少し、筋肉痛が発生します。カッピングは筋肉を伸ばし、血流を増加させ、局所的な痛みの耐性を高め、緊張した筋肉をリラックスさせ、人々の体の痛みや疲労の症状を軽減することができます。 2. 薬物乱用と膿の排出 毒素や膿を排出することも、カッピングの重要な効果の 1 つです。局所的な損傷があり、膿や毒液が出ている場合、カッピングを使用して毒液と膿を直接体外に排出できます。これにより、体内の毒液が除去されるだけでなく、組織細胞の再生が刺激され、傷の治癒が早まります。 3. 体の免疫力を高める 定期的なカッピングは、人体自身の免疫機能を向上させることもできます。カッピング後、皮膚表面に残留うっ血を伴う組織の隙間が現れ、体内の免疫細胞を適切に活性化し、体の抗炎症能力を高め、体内のフリーラジカルの代謝を加速します。このとき、体の免疫力はそれに応じて増加します。 カッピングのデメリットカッピングは人体に多くの利点がありますが、欠点もあります。特に、カッピングを頻繁に行う人は皮膚を傷つけます。ひどい場合には、皮膚感染症やひどいあざを引き起こす可能性があり、皮膚の健康に非常に悪いです。炎症性疾患や出血性疾患を患っている人にとって、カッピングは症状を悪化させ、回復に役立ちません。これはカッピングの一般的な欠点でもあります。 |
推薦する
炊飯器でキビ粥を炊く方法 炊飯器でキビ粥を炊く方法のチュートリアル
炊飯器は、どの家庭にもある小型家電です。お粥を炊いたり、ご飯を蒸したりするのにとても便利です。しかし...
菌類を植えるのに最適な月はいつですか?
キクラゲを植える時期キクラゲの植え付け時期は気温に大きく左右されます。この植物は20〜30℃の環境で...
ココナッツミルクティーの作り方 ココナッツミルクティーの作り方
ミルクティーは多くの女の子に人気です。ミルクの香りが強く、口当たりが滑らかで、とても爽やかです。でも...
ヘンプジュースの選び方は?ヘンプジュースの保存期間はどのくらいですか?
ゴマジュースはゴマペーストとも呼ばれ、夏に最もよく消費される調味料の1つです。もともと、純粋な天然ゴ...
コーンミール粥
皆さんはトウモロコシ粉のお粥についてあまり知らないと思うので、このお粥を紹介したいと思います。コーン...
チューベローズの種を蒔くのに最適な時期はいつですか?
チューベローズの種まき時期チューベローズの種子は通常、気温が徐々に上昇し、日光が十分になる春に播種さ...
ブーゲンビリアの挿し木のやり方
ブーゲンビリアの繁殖方法には、挿し木と挿し木があります。主な繁殖方法は挿し木です。挿し木苗は成長が早...
ユリが咲いた後はどうすればいいですか?どうすれば花を咲かせ続けることができるでしょうか?ユリが枯れた後も鉢植えで育てるにはどうすればいいでしょうか?
ユリは、花を育てるのが好きな人なら誰でも毎年育てるべき植物です。一般的に、ユリの球根は購入して植え付...
ピーマンの漬け方 ピーマンの漬け方
唐辛子は食欲を刺激し、消化を助け、炎症を抑え、細菌を殺し、風邪を追い払い、体を温める効果もあります。...
ワカメの働きとは
昆布の働きは何ですか?多くの友人がこの質問をすると思いますので、以下に答えておきます。ワカメ別名:若...
サツマイモは年に数回植えることができ、収穫には通常数か月かかります。
一年にサツマイモは何シーズン植えられるかサツマイモは年に一度植えることができます。サツマイモは高温多...
左口魚の栄養価、左口魚の薬効と利用法
オヒョウは私たちの生活の中で最も一般的な海水魚です。ヒラメやカレイとも呼ばれています。この海水魚は肉...
おいしいサツマイモの作り方は?サツマイモの食べ方
サツマイモは生活の中で特に人気のある食材です。サツマイモは人体に豊富な栄養を与え、減量にも役立ちます...
冬に豆腐を食べるとどんなメリットがありますか?
冬の主役ともいえる豆腐。毎日のように食卓に並びます。揚げたり、スープにしたり、煮込んだりと、飽きのこ...
牡蠣の食べ方 牡蠣を食べるコツ
牡蠣は一般的な海産物の食材です。柔らかくて栄養価が高く、体に栄養を与え、腎臓と陽を強くします。しかし...