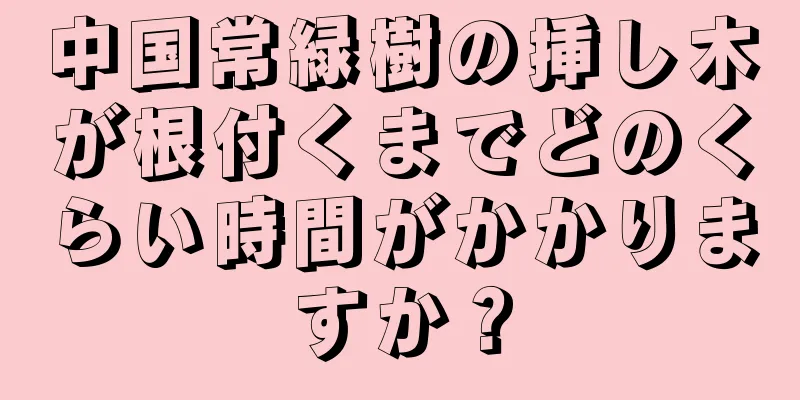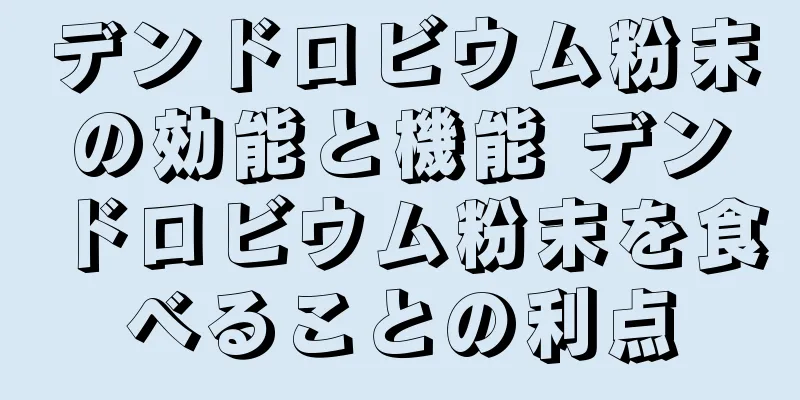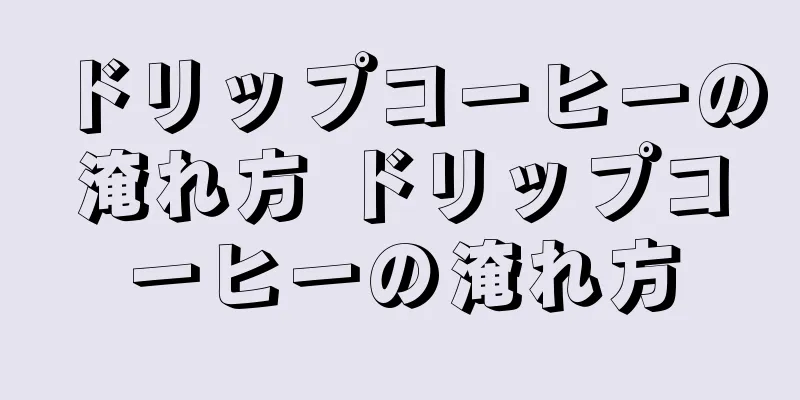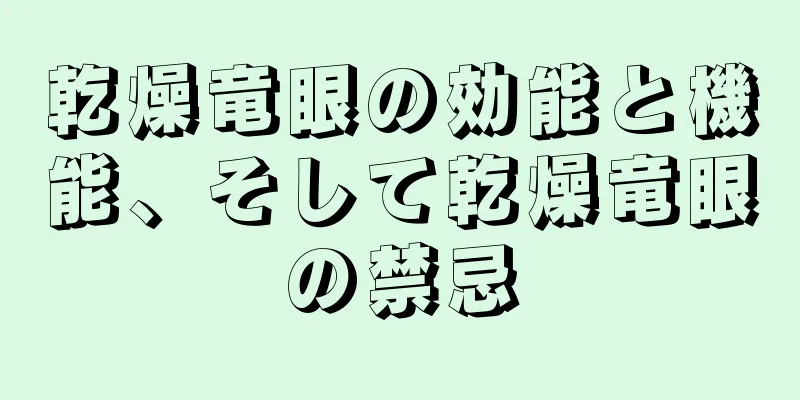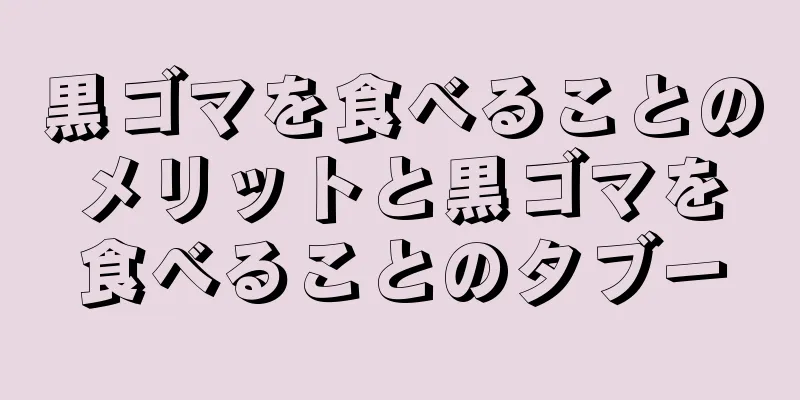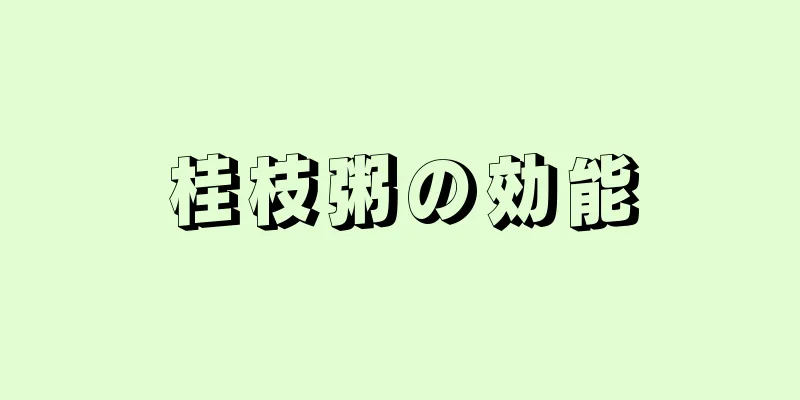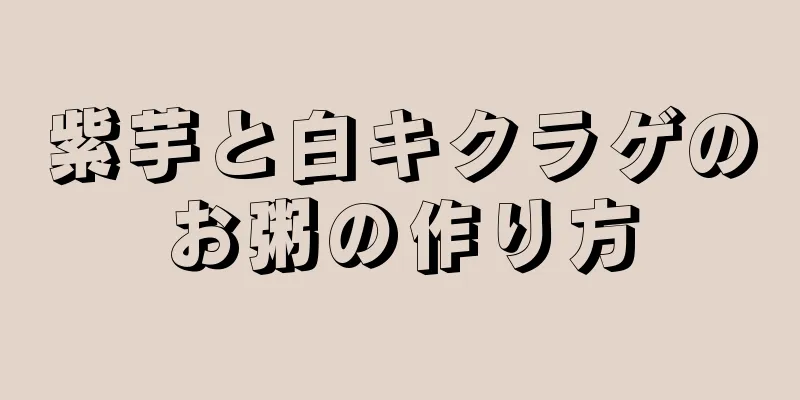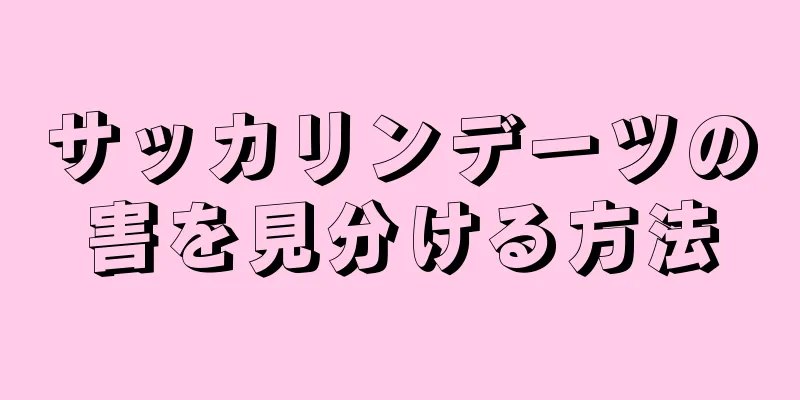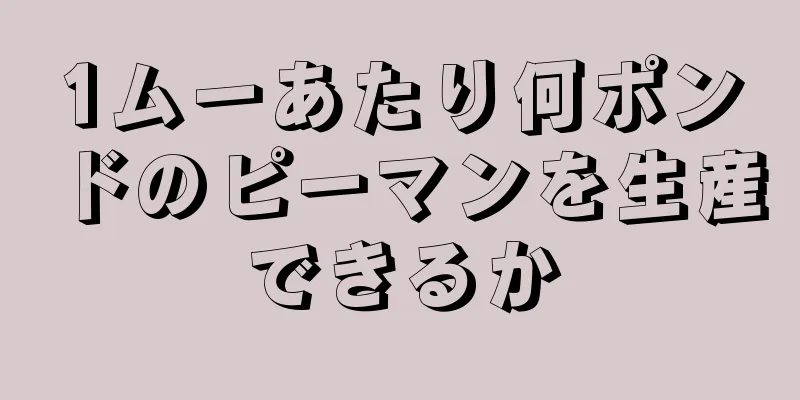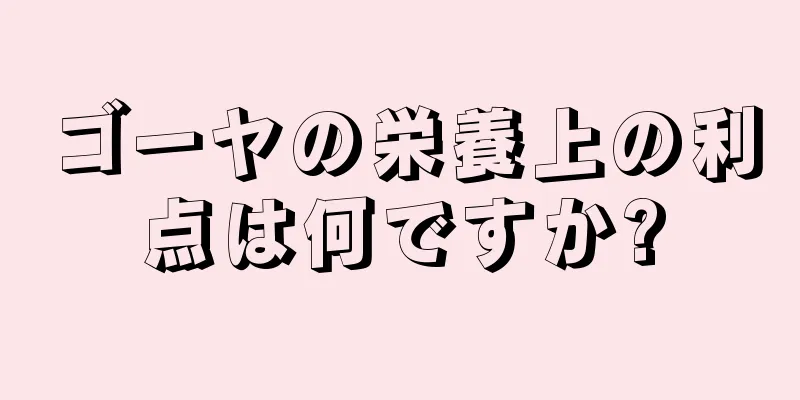ネペンテスの栽培方法 ネペンテスの正しい栽培方法
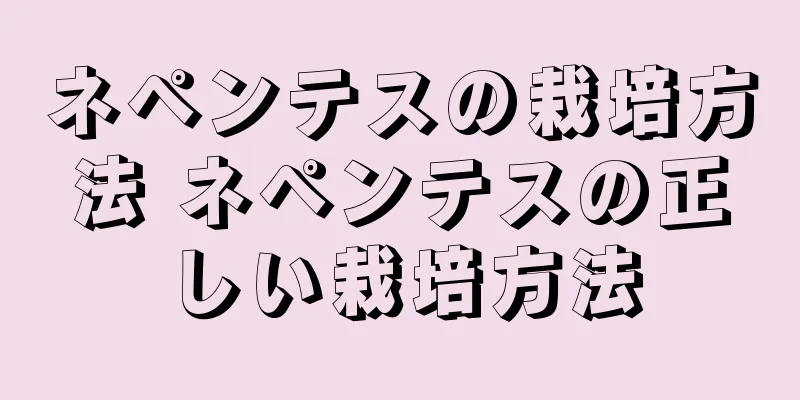
|
ネペンテスは、形が特に美しい、独特の捕虫嚢を持つ珍しい食虫植物です。現在、このタイプの捕虫嚢は主に観賞用植物として栽培されています。しかし、多くの人はネペンテスの栽培方法についてあまり知らず、正しい栽培方法を知りません。しばらくしてネペンテスの正しい栽培方法を書き留めます。これを読んだ後、ネペンテスの栽培方法がわかります。 ウツボカズラの正しい栽培方法1. ウツボカズラの栽培に適した土壌を選ぶ ウツボカズラを育てるときは、適切な土を選ぶ必要があります。ウツボカズラは、緩く、肥沃で、通気性のある土を好みます。鉢植えの場合は、泥炭土、ミズゴケ、木炭、その他の材料を混ぜてもいいでしょう。また、ウツボカズラを育てるときは環境にも注意する必要があります。ウツボカズラは着生植物なので、特に夏は半日陰の環境で育ちます。直射日光に当ててはいけません。 2. ウツボカズラ栽培における肥料と水の管理 ウツボカズラを上手に育てるには、水と肥料の管理が非常に重要です。ウツボカズラは水に特に敏感な植物です。湿度の高い環境でのみ正常に成長し、発育することができます。また、成長期には葉に頻繁に水を吹きかける必要があり、1日に4〜5回が最適です。ウツボカズラは肥料をあまり必要としません。普段捕食している虫が成長に必要な肥料に変わります。しかし、室内で栽培する場合は虫がいないので、適時に肥料を与える必要があります。 3. ウツボカズラの害虫と剪定 ウツボカズラの栽培期間中、いくつかの病気や害虫が発生する可能性がありますが、特に斑点病は非常に一般的です。発生した後、マンコゼブの水和剤を散布することができます。また、ウツボカズラの観賞価値を高めたい場合は、剪定も非常に重要です。特に、変形した葉であるウツボカズラは1〜2か月後に枯れてしまいます。このとき、直接切り取ることができます。そうすることで、植物全体がより美しくなります。 |
推薦する
ドロセラ・カペンシスの繁殖方法と注意点
ケープドロセラの繁殖方法ケープドロセラは挿し木、種まき、冬芽によって繁殖させることができますが、その...
伝統的な中国医学では腎臓を養うために何を食べるべきか
腎臓は生命の源であり、人体で最も重要な臓器です。体が弱っていたり、一般的な病気にかかっている場合、漢...
アルテミシア・カピラリス粥の効能
あなたはヨモギ根粥の効果についてどれくらい知っていますか?以下に詳しく紹介させていただきます。アルテ...
ミモザには数日おきに水をあげるのがベスト
ミモザにはどのくらいの頻度で水をあげればよいでしょうか?春と秋には週に一度ミモザに水をあげるのが最適...
キキョウの栽培方法と栽培技術
ツル性桔梗はつる性の植物で、灯籠桔梗とも呼ばれ、特に華やかな観賞用植物です。この植物の葉はエメラルド...
アロエベラを育てるときに注意すべきことは何ですか?
アロエベラは空気を浄化し、放射線から守ってくれる熱帯植物です。栽培も簡単なので、自宅で育てる人も多い...
トマトを食べるとどんなメリットがありますか?
トマトを食べると私たちにどんなメリットがあるのでしょうか? 以下でそのメリットについてお話しします。...
エッグタルト液の作り方は?
エッグタルトはパイのように甘くて美味しいです。エッグタルトなどの洋風パイを作る上で最も重要なのは、エ...
尿素とリン酸二水素カリウムを葉面散布肥料として一緒に散布する(一緒に使用しても効果的か)
米や麺類などの主食に加えて、肉や野菜、果物などの副食も食べます。農作物についても同様です。窒素、リン...
エビと一緒に食べてはいけないものは何ですか?エビを食べるときの注意点
エビの皮は非常に一般的な食材です。さまざまな方法で食べることができ、栄養価が非常に高く、カルシウムを...
ジャスミンの剪定方法
ジャスミンの剪定時期ジャスミンは通常、花がすべて枯れてから 10 日以内に剪定できます。ジャスミンの...
犬用デーツの栄養価と効能
犬ナツメは中国黒龍江省で生産される野生の果物で、「小さなキウイ」とも呼ばれています。見た目は緑色で、...
ダンシング・ウィズ・グレース多肉植物の育て方
ダンシングプラントはもともと南アフリカで分布していました。スベリヒユ科スベリヒユ属の変種です。花が美...
桃の栄養情報
桃は昔から多くの人に愛されてきました。桃好きの私たちは、桃の栄養成分について学んでみましょう。桃には...
カボチャ粥のレシピとカボチャ粥の治療効果
カボチャ粥は昔から胃にとても栄養のある食事です。カボチャ粥はキビと米を混ぜて作られ、粥自体の味が一層...