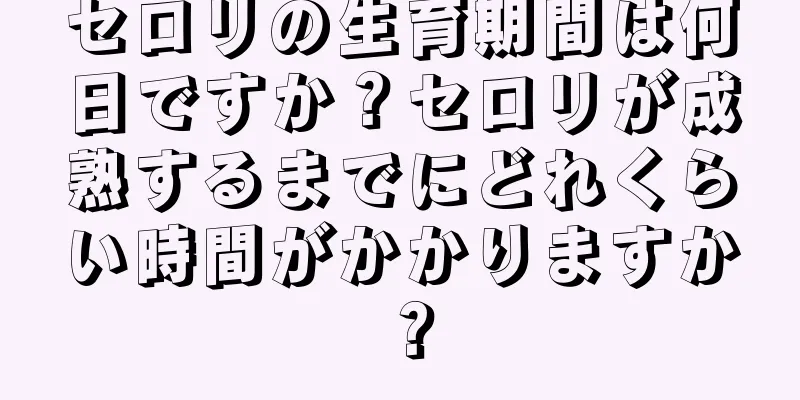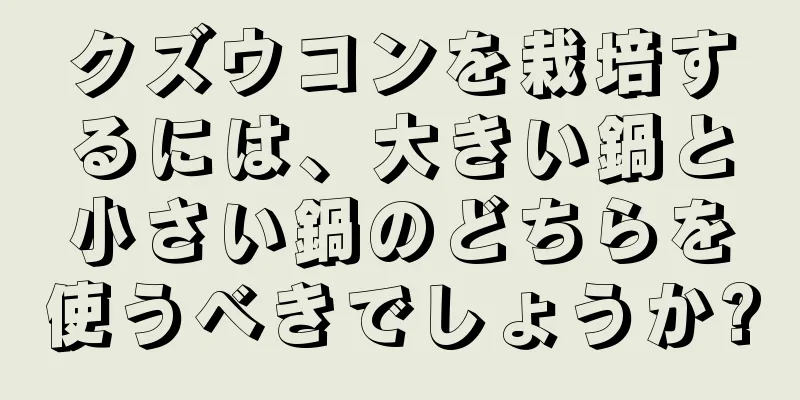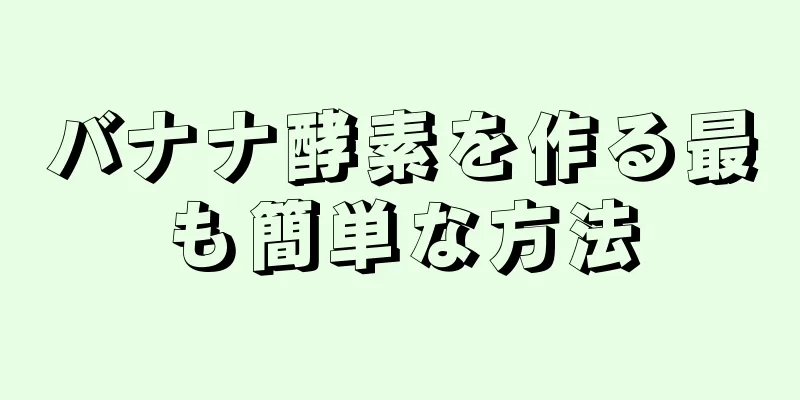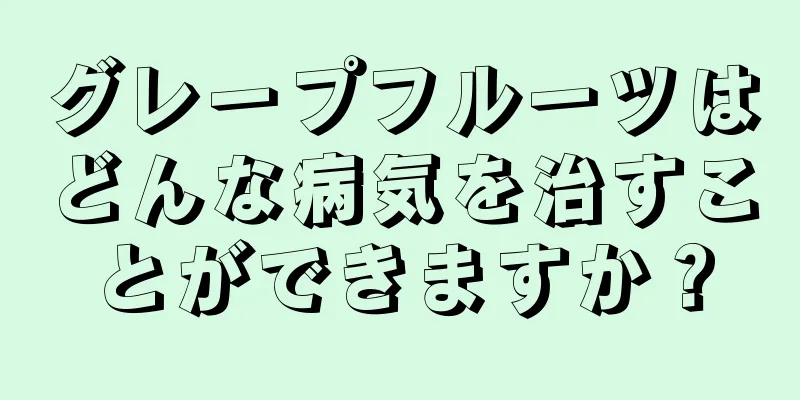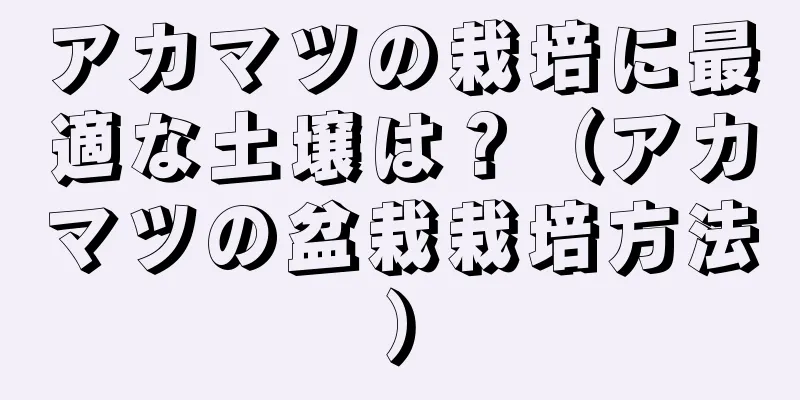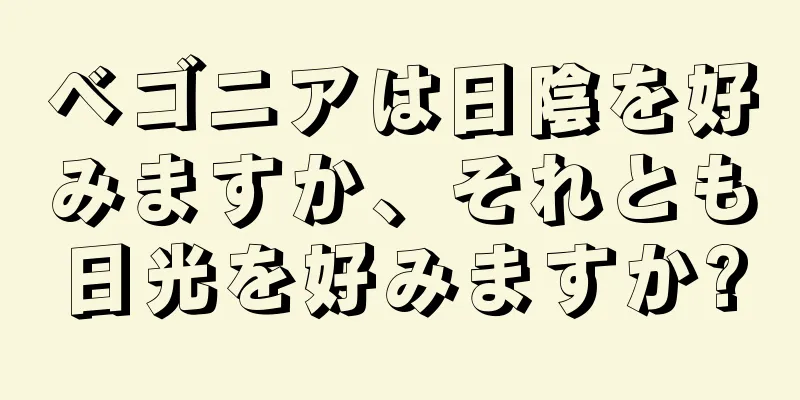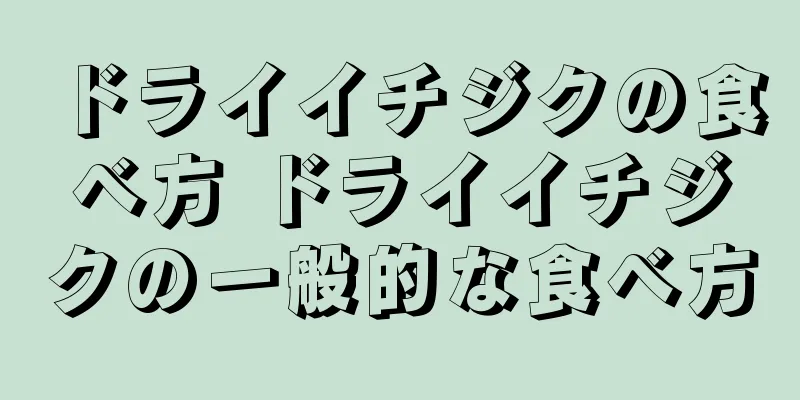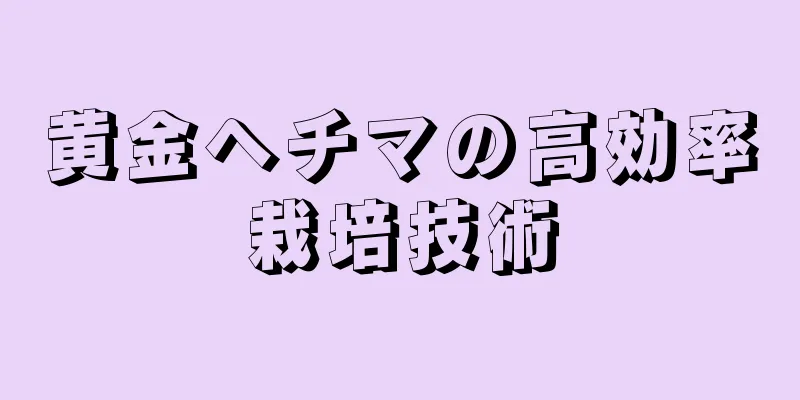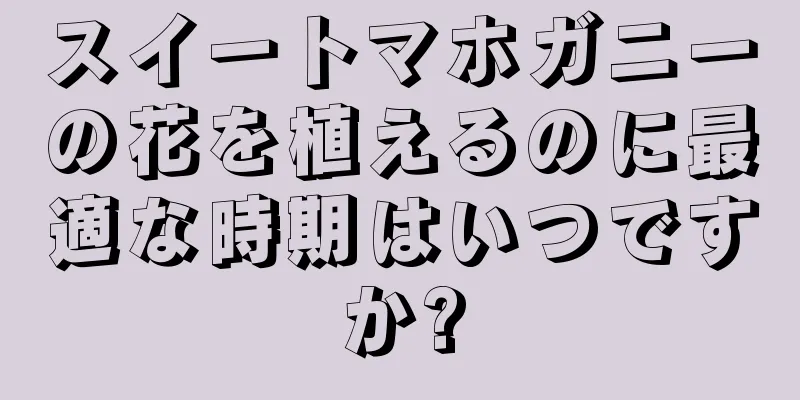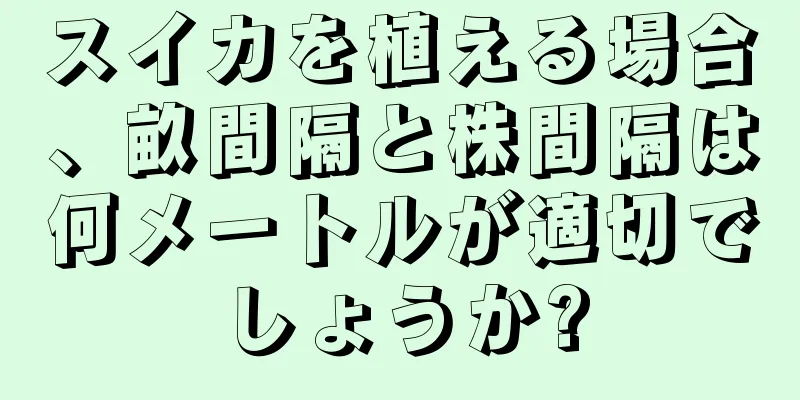茹でた栗の皮の剥き方 茹でた栗の皮の剥き方
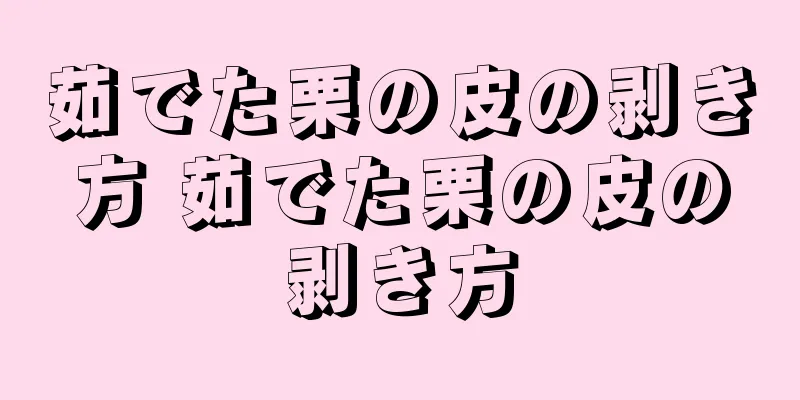
|
私たちの日常生活では、新鮮な栗を食べるのが好きな人がたくさんいます。新鮮な栗を買ったら、鍋に入れて調理することがよくあります。しかし、調理した栗の殻をむくのは大きな問題になります。どうすればよいでしょうか?栗の殻を剥く最も早い方法は何ですか?これについてもっと詳しく知りたい場合は、私と一緒に見に行ってください。 茹でた栗の皮の剥き方1. 冷水処理法 栗を調理した後、素早く殻をむきたい場合は、調理した栗を取り出し、洗面器に入れた冷水に直接3〜5分ほど浸します。次に、はさみで栗の表面に穴を開け、手で直接殻をむきます。この殻割り方法は、熱膨張と収縮の原理を借用したものです。 2. 凍結処理法 茹でた栗の殻を早く取り除きたい場合は、冷凍保存という方法もあります。一番良い方法は、茹でた栗を取り出し、冷ましてから冷蔵庫の冷凍庫に直接入れて保存することです。保存時間は2~3時間です。このようにして、低温環境では栗の身と殻が自然に分離します。取り出した後、手で軽くつまむだけで殻を取り除けます。栗の身は特に完熟したものになります。 3. ナイフカット法 栗の殻をむく方法は他にもあり、これも比較的簡単です。栗を取り出し、お皿に置き、ナイフで真ん中を切ります。栗は二つに分かれ、中の新鮮な栗の果肉が見えます。手で軽く押すと、自然に殻から離れ、おいしい栗の果肉を食べることができます。 4. ノッチング法 茹でた栗の皮を早く剥きたい場合は、鍋に入れて茹でる前に、はさみで栗の殻に十字の切り込みを入れます。そして鍋に入れて茹でます。茹で上がったら、小さな穴が自動的に開きます。その後、小さな穴に沿って殻を破り、中の果肉を取り出します。 |
>>: ドライライチの効能と機能、そしてドライライチのタブー
推薦する
ヤシの木の種を植えるのに最適な時期はいつですか?
ヤシの木の種まき時期ヤシの木は多年生植物です。種は播種後約1週間で発芽します。ヤシの木の成長サイクル...
マネーグラスの副作用とタブー、そしてマネーグラスを栽培することの利点
マネーワートは私たちの生活の中で最も一般的な緑の観葉植物です。常緑で生命力が強いため、鉢植えにして室...
キウイピューレの実践と効能
キウイはビタミンCが豊富な高級フルーツとして知られています。特に栄養価が高く、甘酸っぱい味で生でも食...
大豆水の効能と働き 大豆水の作り方
大豆は私たちの日常生活にとてもよく見られます。豆腐や豆乳などの大豆製品を作るのに使われるほか、水で煮...
ディオールの香水の保存期間
ディオールの香水はフランスでは非常に高い地位を持つ香水ブランドであり、その人気はシャネルの香水に劣り...
ツツジにはどのくらいの頻度で水をあげるべきでしょうか?頻繁に水をやる必要がありますか?
ツツジにはどのくらいの頻度で水をあげるべきでしょうか?シャクナゲは水浸しを非常に恐れます。水やりをす...
赤グアバの効能と効果、そして赤グアバを食べることの効能
レッドハートグアバはグアバとも呼ばれ、熱帯地域で生産される一般的な果物です。果肉は新鮮で柔らかく、ほ...
乾燥ショウガの効果と機能は何ですか?乾燥ショウガを食べるとどのようなメリットがありますか?
干しショウガは伝統的な漢方薬の一種で、人々が普段食べている薬味ショウガと同じ植物から採取されますが、...
ツツジの育て方 ツツジの育て方と注意点
多くの庭園の景勝地では、ツツジが咲いているのをよく見かけます。ツツジは色が鮮やかで、香りが魅力的で、...
ヒナギクにはどのくらいの頻度で水をあげればよいでしょうか?
ヒナギクにはどのくらいの頻度で水をあげればよいでしょうか?春は成長が旺盛な時期なので、土壌を湿らせ、...
五穀粥
ウー・レン・ポリッジについてどれくらい知っていますか?以下に詳しく紹介させていただきます。五穀粥中国...
クラブアップルにはどのくらいの頻度で水をあげればよいでしょうか?
クラブアップルにはどのくらいの頻度で水をあげればよいでしょうか?ベゴニアは特に水を好む植物ではありま...
ピンクミューリーグラスを植えるのに最適な月はいつですか?
ピンクミューリーグラスを植える時期ピンクミューリーグラスは通常春に植えられ、2月と4月に植えるのに適...
平和の木に肥料を与えるのに適した肥料は何ですか?ピースツリーを育てるための養液と肥料は3種類あります。
平和のユリは肥料を比較的多く必要とします。一般的には化成肥料、有機肥料、鶏糞分解肥料、米発酵水などが...
蚕の蛹の効能と機能、蚕の蛹を食べることの禁忌
蚕の蛹は栄養価の高い食材です。1400年以上前から人々の食卓に上っていたと言われています。現在でも非...