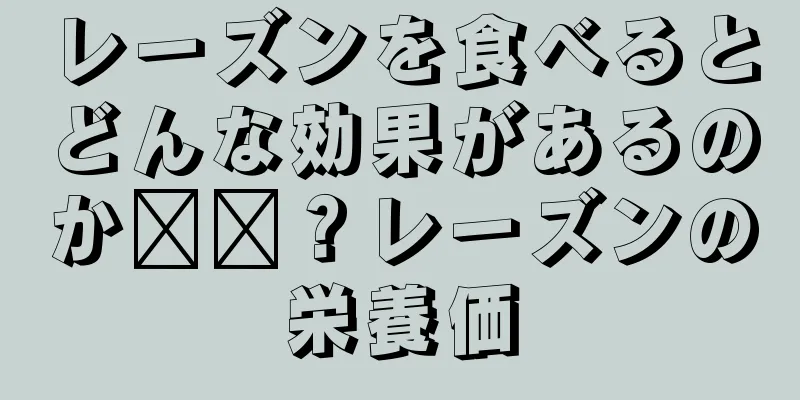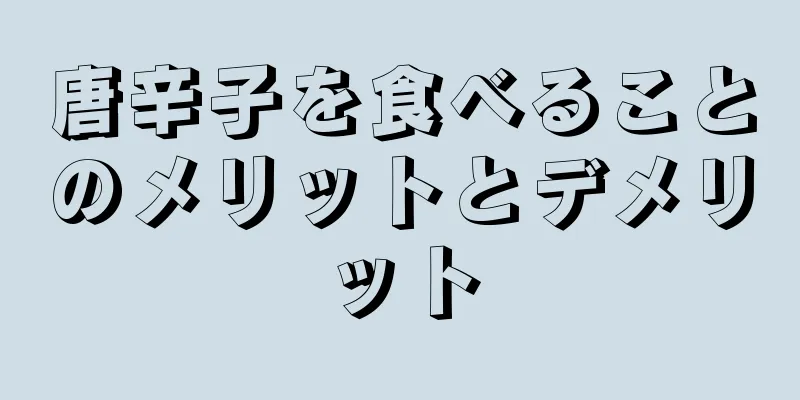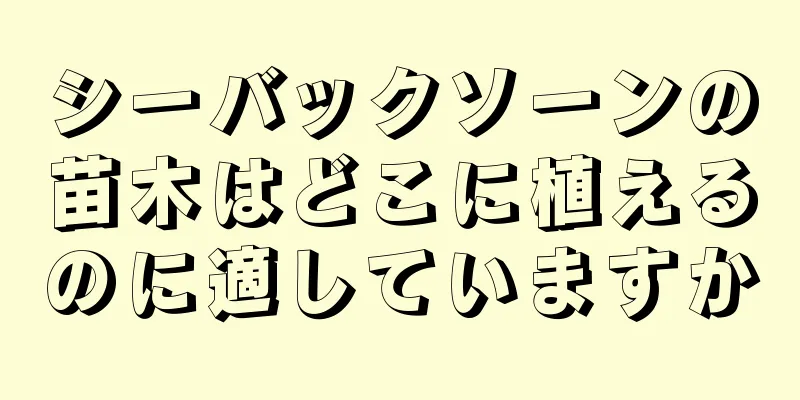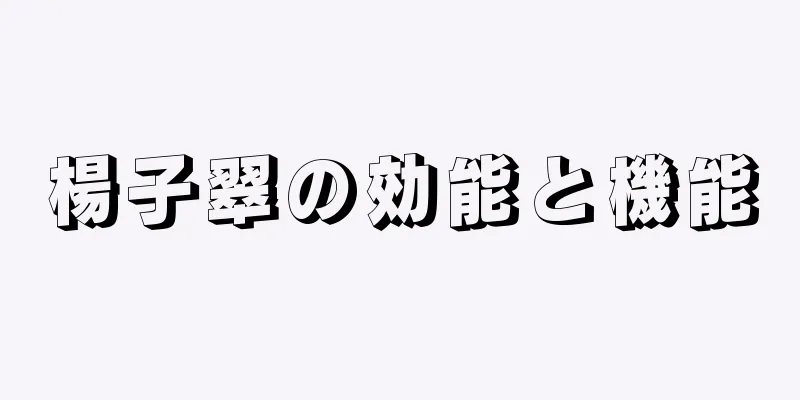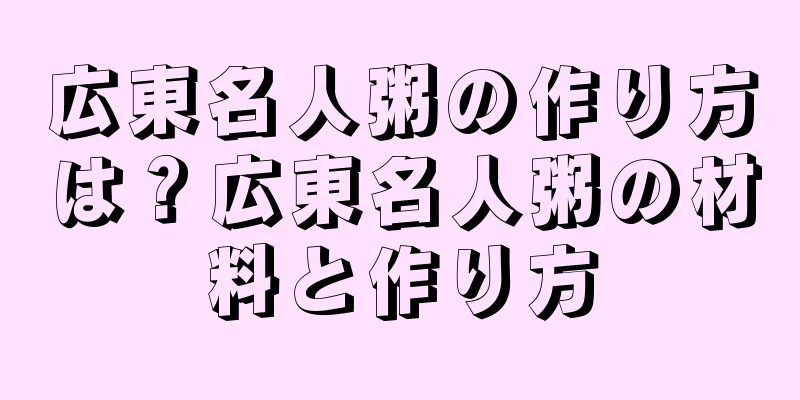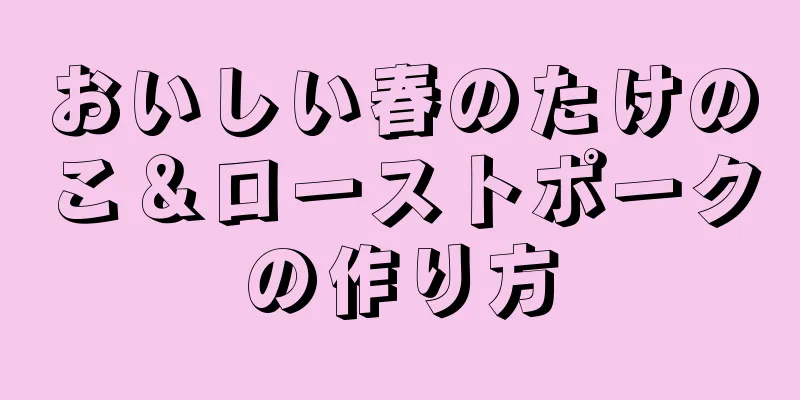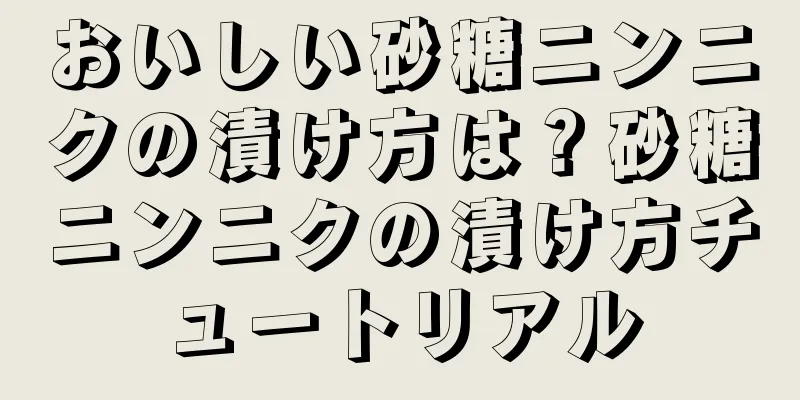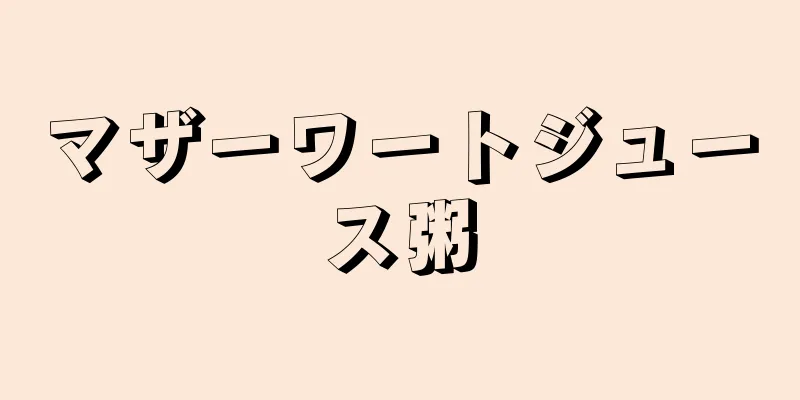どじょう粥の作り方
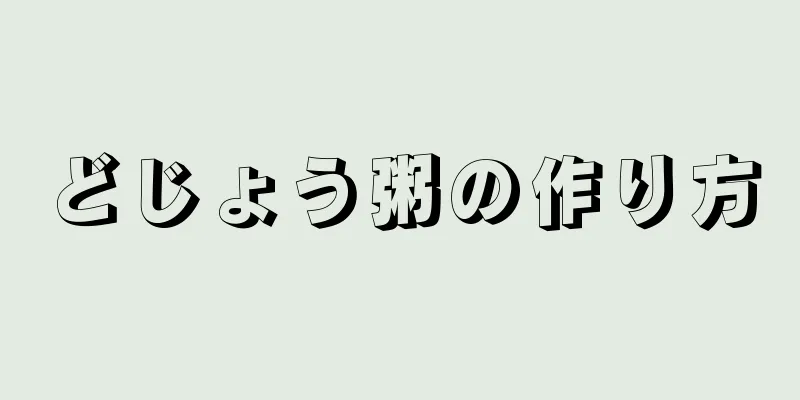
|
どじょう粥の作り方にとても興味を持っている友人は多いと思います。以下で一緒に学びましょう。 どじょう粥の材料料理と効能:高級主食、腎養生レシピ、気血養生レシピ、胃養生レシピ、栄養失調レシピ。プロセス:煮たドジョウ粥。材料:主な材料:米300g、ドジョウ1000g 付属品: ピーナッツ(生)100g、赤野菜50g 調味料: コリアンダー3g、ネギ5g、ピーナッツオイル5g、塩5g、砂糖3g 生どじょう粥の特徴は、さっぱりとしたスープと柔らかい身。 どじょう粥の作り方1. 米を洗い、塩で味付けします。 2. 鍋に水を加えて沸騰させ、ピーナッツの粒と一緒に調理します。 3. ドジョウの背びれと背骨を切り落とし、内臓を取り除き、洗って水気を切ります。 4. ドジョウに少量の食用油、塩、醤油、砂糖を混ぜます。 5. お粥がほぼ完成したら、味付けをして混ぜ合わせたドジョウを加えて火が通るまで煮ます。 6. 盛り付ける前に、みじん切りにしたネギ、コリアンダー、ネギを散らします。相性の悪い食べ物:米:唐孟神:「日本米は馬肉と一緒に食べると腫瘍の原因となるため、一緒に食べることはできません。また、突然の心臓の痛みを引き起こすため、キバナバチと一緒に食べることもできません。」 清朝の王玉英:「チャーハンは香りが良いが、乾燥していて火を刺激する。風邪や下痢を患っていない人は避けるべきである。」 ドジョウ:ドジョウは犬肉と一緒に食べてはいけません。犬の血とドジョウは相性が悪く、陰虚火虚の人は食べないようにしてください。カニとドジョウは相性が悪く、機能が正反対なので一緒に食べてはいけません。毛ガニとドジョウは相性が悪く、一緒に食べると中毒を引き起こします。 ピーナッツの粒(生):胃が弱い人は、ピーナッツをキュウリやカニと一緒に食べないでください。そうしないと、簡単に下痢を引き起こします。 |
推薦する
風邪に効く果物は何ですか?
風邪の一般的な症状。風邪や咳の症状を改善するために、多くの人は薬を飲みたがらず、代わりに民間療法を使...
大根団子の作り方
多くの人の目には、大根は漬物に最適な選択肢です。実際、大根の食べ方はさまざまです。炒め物やスープにす...
ヨモギゆで卵の作り方
ヨモギでゆでた卵は、中国の民間で最も長い歴史を持つ薬用食品です。女性の月経困難症を和らげるだけでなく...
ブーゲンビリアは砂の中に植えられますか?
ブーゲンビリアは砂の中に植えられますか?ブーゲンビリアは植えるときに、さまざまな材質の土壌に一定の適...
かぼちゃと大麦のお粥の作り方
かぼちゃと麦のお粥の作り方は実はとても簡単です。以下に編集部が用意した内容をご覧いただければ、きっと...
タマネギとニンニクの効果、機能、栄養成分
日々の料理に玉ねぎとニンニクは欠かせません。多くの料理は、おいしくするためにこれらの調味料を加える必...
菜種油の効能と機能
菜種油は、黄金色で透明で澄んだ液体で、人間が食べられる植物油です。植物界の花の成熟した種子を主原料と...
栗の皮の薬効と副作用
栗は誰もが食べたことがあるはずです。栗は甘くて栄養価が高く、栄養価の高い食べ物であることは誰もが知っ...
レタスの栄養価と効能
レタスはキク科の植物で、食用の根菜です。私たちの日常生活では非常に一般的です。さわやかでシャキシャキ...
キャベツの種はどこから来るのでしょうか?
キャベツの種の入手方法キャベツの種は果実の中で成長し、露出しません。キャベツの種子を得たい場合には、...
ほうれん草とピーナッツを酢で調理する方法
ほうれん草とピーナッツは生活の中で最もよく見かける食材ですが、一緒に食べる機会はあまりありません。今...
高麗人参の実の植え方と時期 高麗人参の実を植えるのに最適な時期はいつですか?
高麗人参の実を植える時期は、毎年3月から8月の春と夏が最適です。植える際には、日当たりの良い丘の斜面...
ジュージュー焼けるナス
焼きイカや焼きナスを食べたことがありますか?今日はその作り方をご紹介します。材料材料: ナス2本、豚...
豆腐脳の効能と機能
皆さんは豆腐プリンを食べたことがあるでしょうか?老豆腐とも呼ばれ、中国の名物料理の一つで、多くの地域...
球根フェンネルの植え付け時期と方法栽培と管理技術
フェンネルの球根を植える時期球根フェンネルは私の国の多くの地域で栽培されています。十分な日光と涼しい...