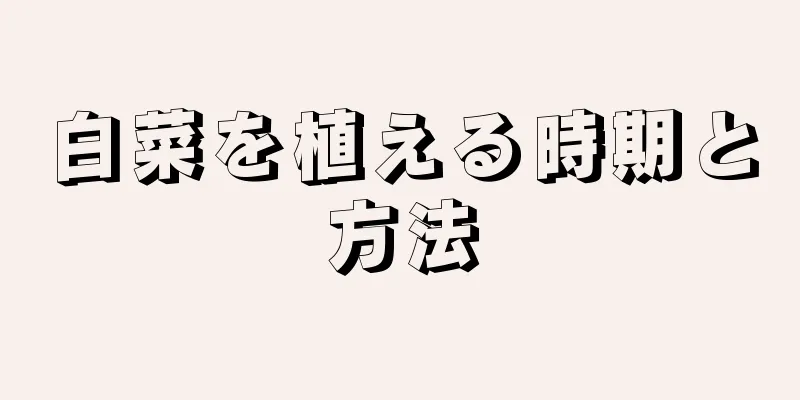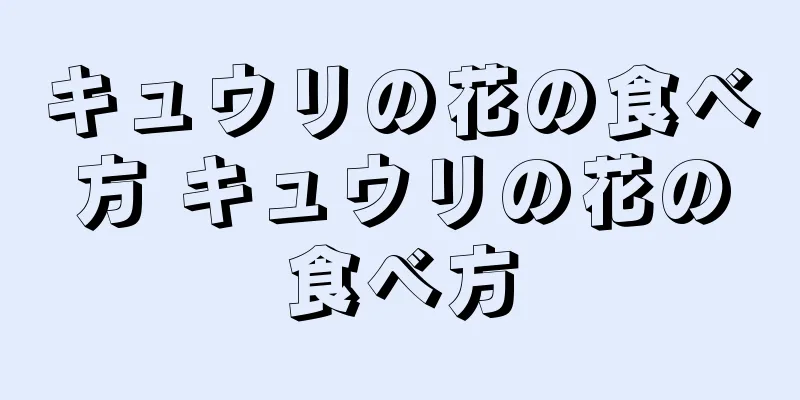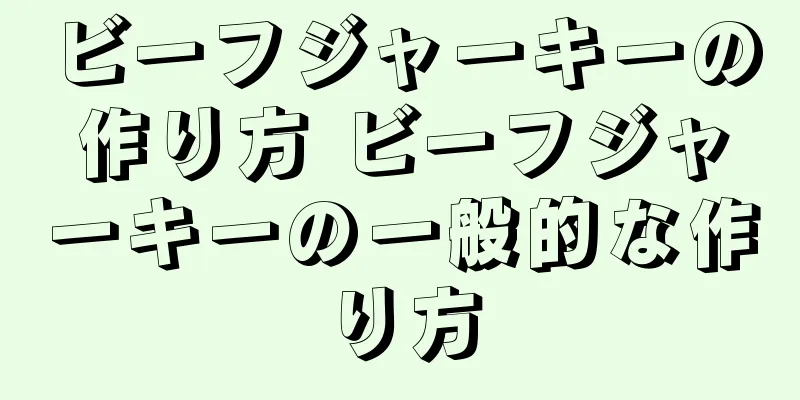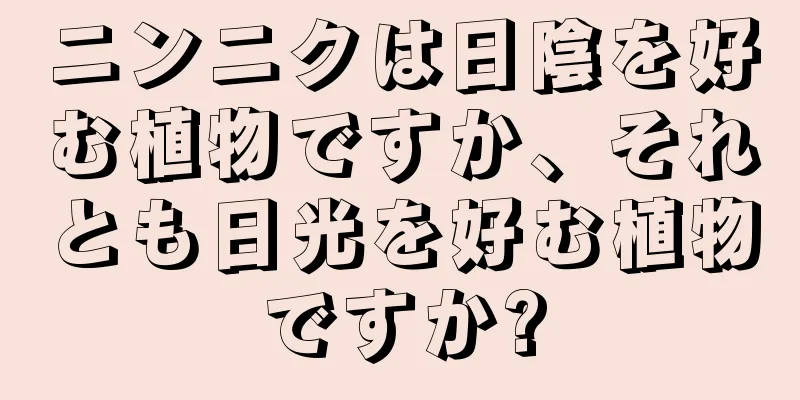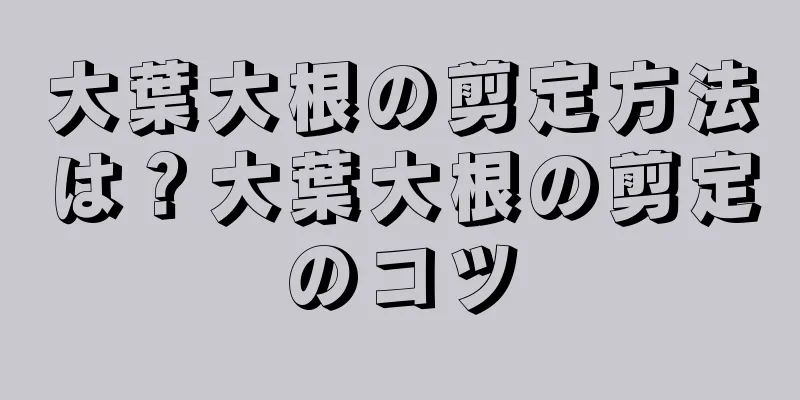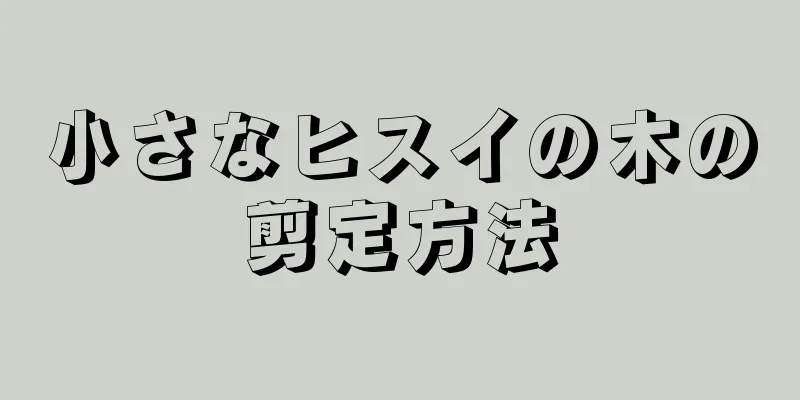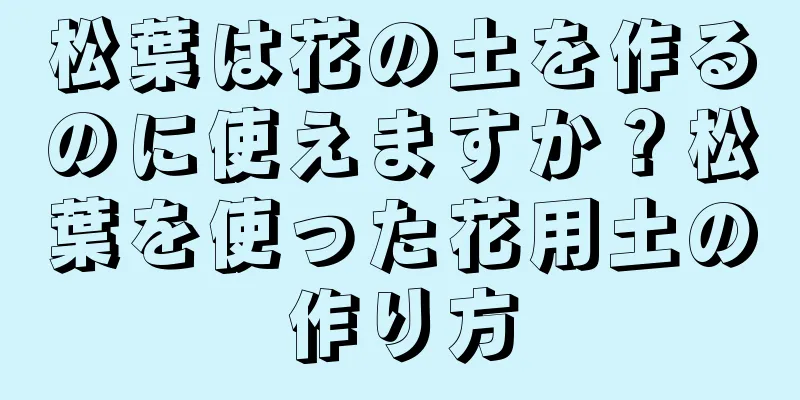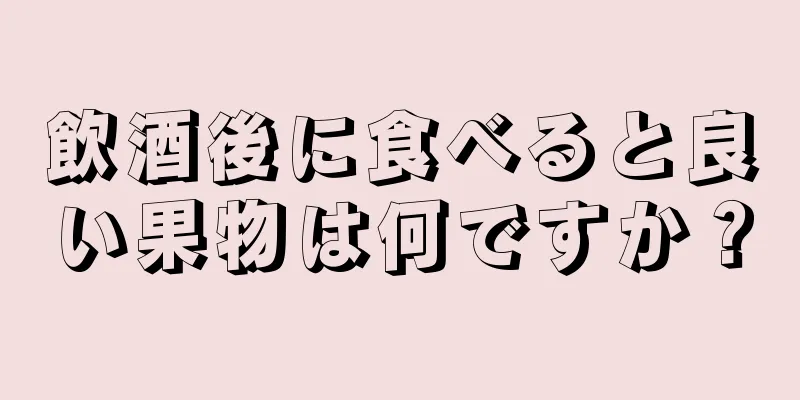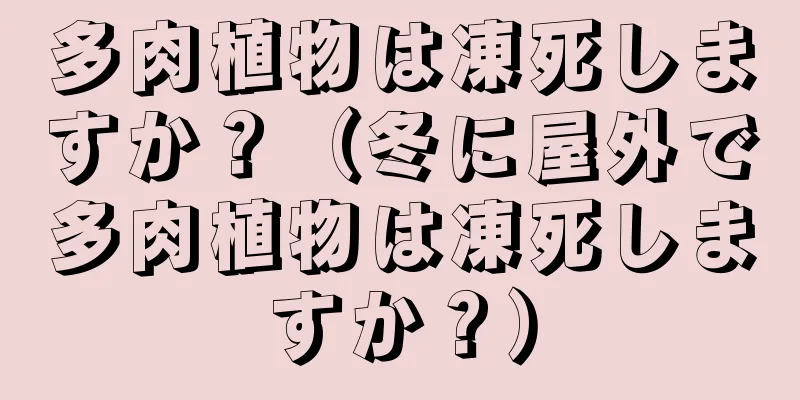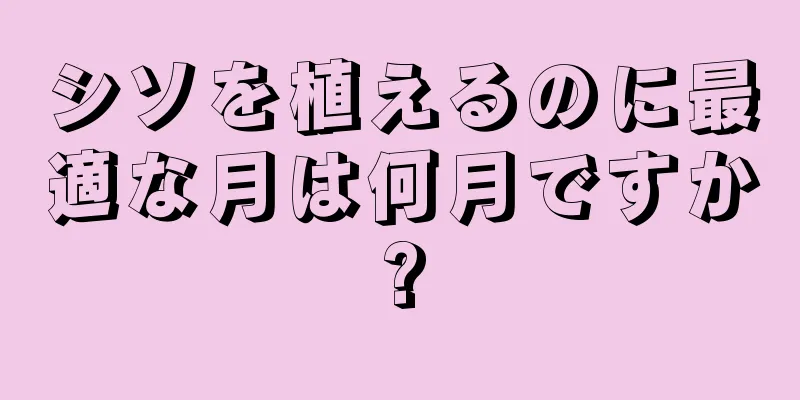焦三仙粥
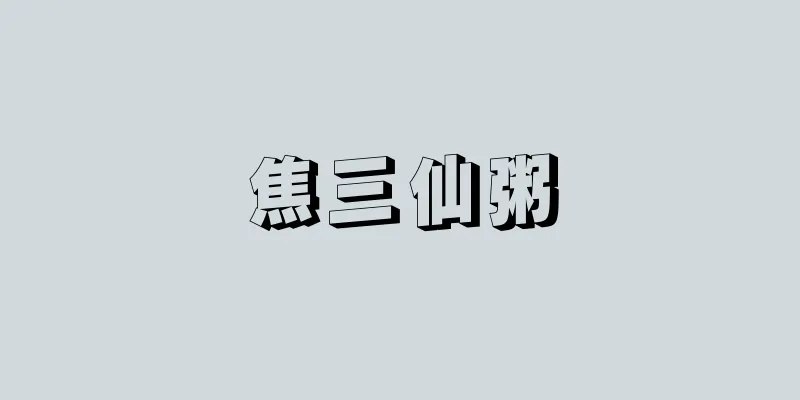
|
多くの友人が焦三仙粥を飲んだことがあると思います。下記の詳しい紹介をご覧ください。気に入っていただければ幸いです。 焦三仙粥出典:「お粥のレシピ」 材料:神曲、麦芽、サンザシ各10~15グラム、精白米50グラム、砂糖適量。 焦三仙粥の作り方まず、神曲、麦芽、サンザシを鍋に入れて煮て濃い汁を出し、残渣を取り除き、白米と砂糖を加えてお粥を作ります。 使用方法: 食事の間に軽食としてお召し上がりください。 効能:脾臓と胃を強化し、食積を解消し、瘀血を解消します。食滞、腹痛、下痢、乳児や小児の食物の消化不良などに適しています。 注意: 空腹時に服用しないでください。 ジャポニカ米の栄養成分 ジャポニカ米は、米や精白米としても知られています。ジャポニカ米には、デンプン、タンパク質、脂肪、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンC、カルシウム、リン、鉄などの必須栄養素が含まれており、人体に必要な栄養素とカロリーを供給できます。玄米には白米よりも多くのタンパク質、脂肪、ビタミンが含まれています。米ぬか層に含まれる粗繊維分子は胃腸の運動を助け、胃の不調、便秘、痔などの消化管疾患に一定の治療効果があります。健康維持と寿命の延長のために日本米でお粥を調理する習慣は、2,000年以上の歴史があります。お粥の中の最上層の粥油は水分と精気を補給することができ、病人、産後の女性、高齢者に最適です。 ジャポニカ米の治療効果 ◆ジャポニカ米には、脾胃を強化し、中気を補い、陰を滋養し、体液を促し、落ち着きのなさを和らげ、喉の渇きを癒し、腸を強化し、下痢を止める効果があります。脾胃虚弱、喉渇き、栄養失調、病後虚弱などの症状に用いられます。 ◆日本粥は「人を養うのにこの世で最も優れたもの」として知られており、適度に定期的に食べる必要があります。 ◆玄米は白米よりも栄養価が高く、コレステロールを下げ、心臓発作や脳卒中のリスクを軽減します。 |
推薦する
韓国風チリソースの作り方
韓国のチリソースのレシピをいくつかご紹介します。 01 韓国風チリソース材料:もち米粉60g 水60...
栗の粉の作り方は?栗の粉をペースト状にする方法
新鮮なヒシの実を収穫した後、殻を剥いてそのまま蒸すと甘いスープを作ることができ、人体に豊富な栄養を与...
なぜ牛の腎臓を食べないのか?牛の腎臓の害
私たちの日常生活では、牛肉、ステーキ、子牛を食べるのが好きな人はたくさんいますが、牛の腎臓に興味があ...
キャベツの植え方と植える時期
キャベツの植え付け時期春キャベツは秋から冬にかけて育て、冬に移植し、翌年の春に収穫することができます...
赤アマランサスの効能と機能。赤アマランサスを食べてはいけない人は?
赤アマランサスは野生のハーブです。人々がその健康価値を発見した後、市場の需要は増加し続けました。現在...
キヌアの生育環境と地域の状況
キヌアの栽培環境と条件キヌアは涼しい環境での栽培に適しています。お手入れの際は十分な光が必要です。比...
トマトの生育環境要件、どのような場所でトマトを栽培できるか
今日はトマトの栽培環境の要件についてお話します。 (1)温度:トマトは好熱性野菜です。通常の条件下で...
カレー粉の使い方は?カレー粉の正しい使い方
カレー粉は黄色い粉で、生活の中で非常に一般的なスパイスです。主な原料としてターメリック、コショウ、ク...
冬のホヤのお手入れ方法
ホヤは凍結が怖いですか?ホヤの生育に適した温度は18~28度です。冬は凍結する恐れがあります。気温が...
紫芋の栄養価と食べ方
紫芋は紫サツマイモとも呼ばれ、皮が紫色で肉質が紫色のジャガイモで、ジャガイモ科の中で最も栄養価が高く...
ブロッコリーが発芽するのに何日かかりますか?ブロッコリーは種を蒔いてから発芽するまで何日かかりますか? (育苗工程)
ブロッコリーが発芽するまでにどれくらい時間がかかりますか?ブロッコリーの種は約6〜8日で発芽します。...
おいしい豚肉と緑の野菜炒めの作り方 豚肉と緑の野菜炒めの材料と作り方
緑色野菜は非常に一般的で栄養価の高い野菜です。ほとんどの南部の人にとって最も人気のある野菜です。特に...
貯金袋に肥料を与えるのに最適な肥料は何ですか?お金持ちが鉢植えに好む2つの肥料
金のなる木は肥料を比較的多く必要とします。肥料を与える際には、施肥の時期、方法、量に注意する必要があ...
干しタケノコの栄養価と効能
干しタケノコは、新鮮なタケノコを乾燥させて加工したもので、栄養価が最大限に保たれており、生のタケノコ...
湯葉の栄養価と効能、湯葉を食べるメリット
湯葉を食べたことがありますか?その効果と機能をご存知ですか?東北地方で多く生産される大豆を原料とした...