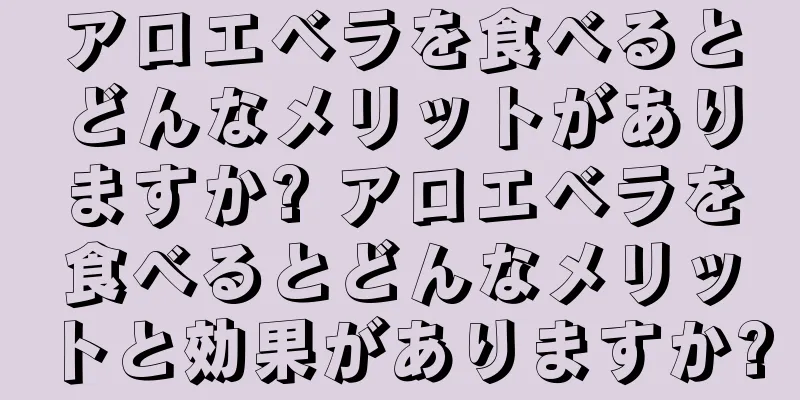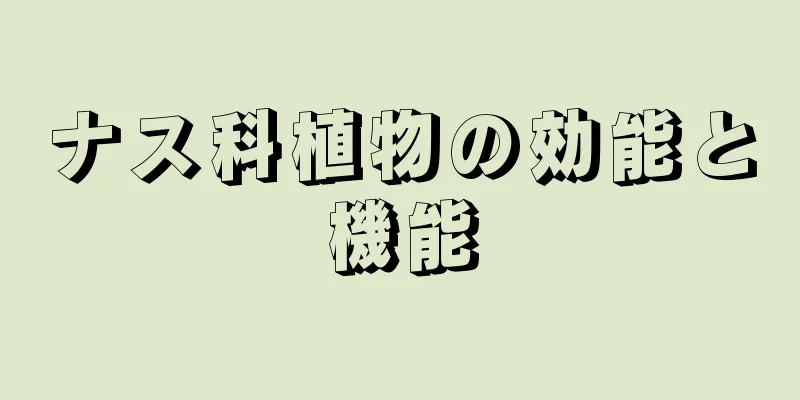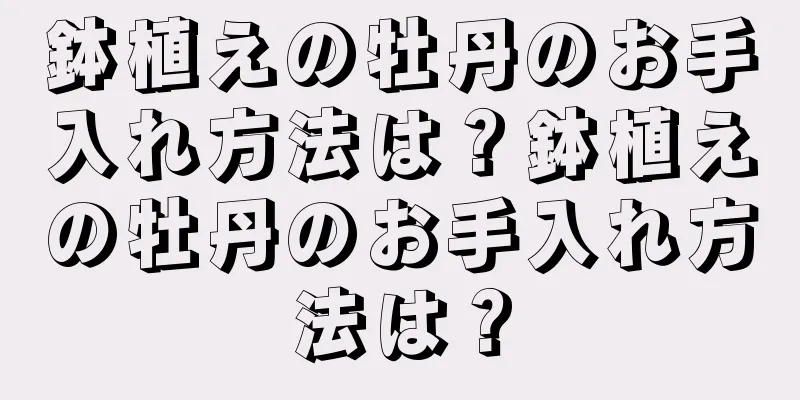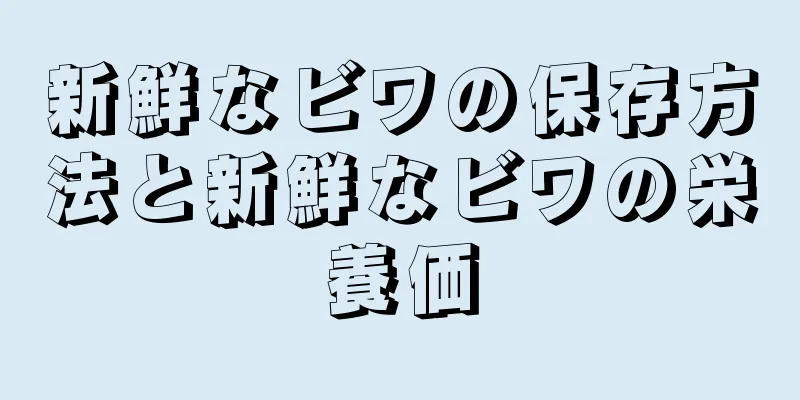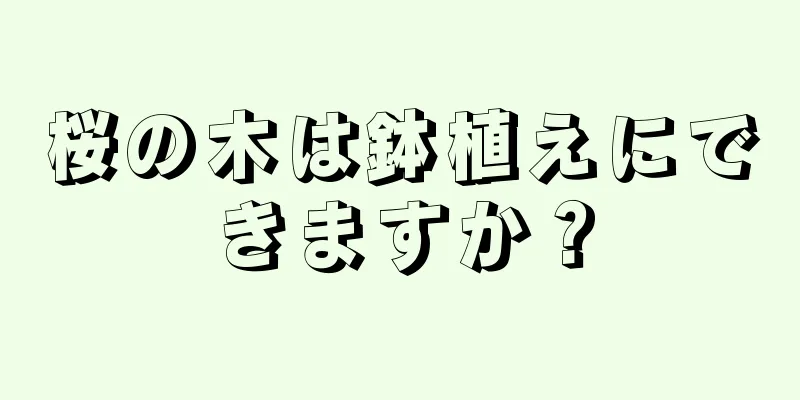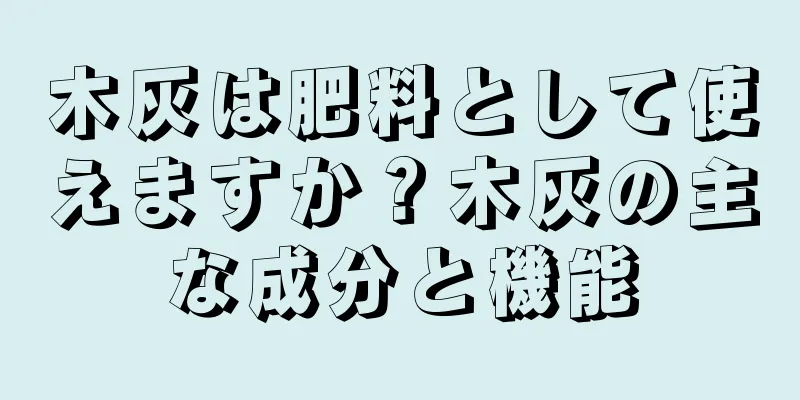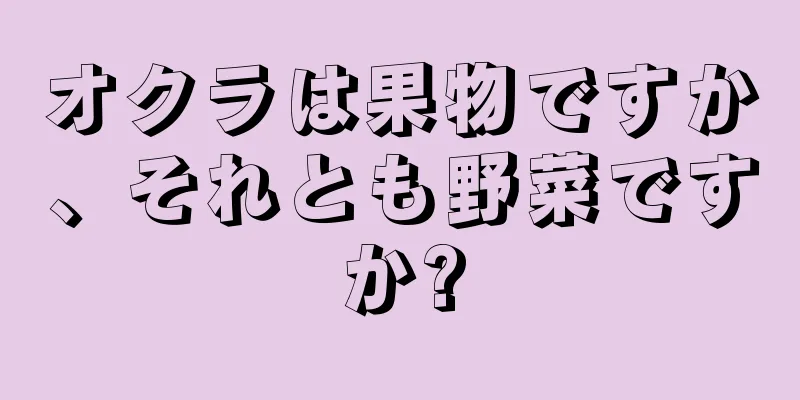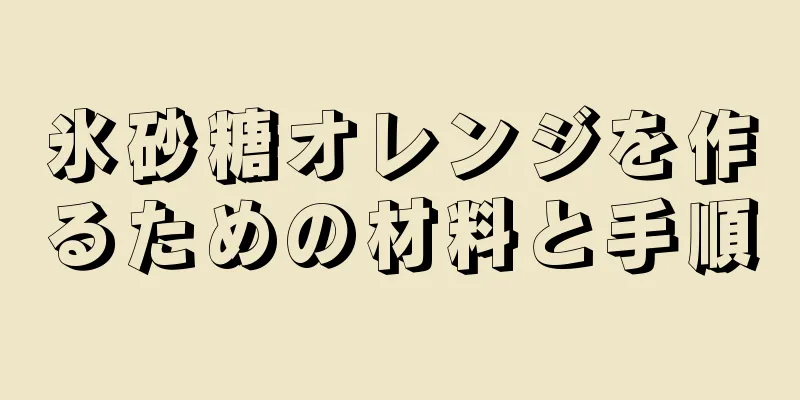レンズ豆はどんな病気を治すことができますか? レンズ豆の民間療法は何ですか?
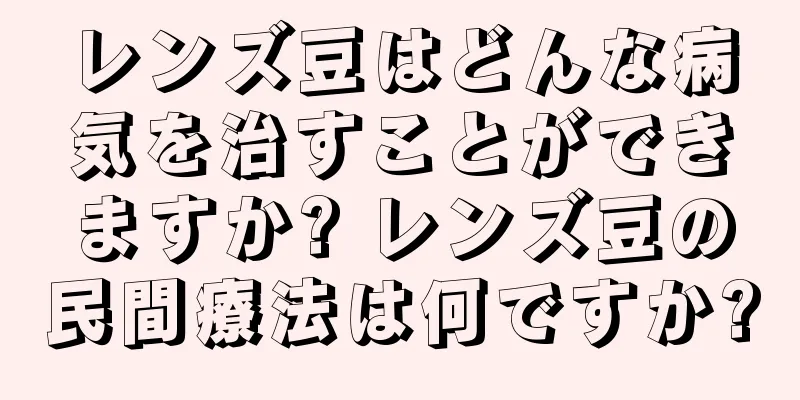
|
白レンズ豆は食用であるだけでなく、非常に優れた薬用素材でもあります。病気の治療に使用できます。それでは、白レンズ豆の処方についてお話ししましょう。 1. 浮腫の治療:適量のレンズ豆を黄色くなるまで炒め、粉末状にして瓶詰めし、後で使用する。成人は1回あたり9g、小児は1回あたり3gを服用します。毎日、朝食、昼食、夕食の前にイグサの煎じ汁を飲んでください。 2. 下痢の治療:レンズ豆30gと緑豆50gを一緒に炊いてお粥にし、空腹時に好きなだけ食べます。鍋にレンズ豆30gと適量の水を入れて煮てレンズ豆のスープを作り、お茶として飲みます。 3. ヘビに噛まれた場合の治療:レンズ豆の根と白ワイン(水)適量。粗い磁器のボウルか乳鉢に白ワイン(または水)を加え、ワインの色が茶色になるまで、ジュースとレンズ豆の根をすりつぶします。 1日3回、1回につきワインを1杯飲みます。 4. 白帯下の治療:適量のレンズ豆を水で煮て、お茶として飲みます。 5. 腎炎の治療:レンズ豆50gを水250mlに入れて、残り100mlになるまで煮ます。1日1回、7~10日間服用してください。1回の治療後、2~3日後に2回目の治療を行ってください。 6. コレラ、嘔吐、下痢の治療:レンズ豆6gを潰し、酢と混ぜて食べます。 7. 熱を和らげ、湿気を取り除くために使用します。レンズ豆9g、ポリアココス、ポリアココス、アトラクチロデスマクロセファラ各9g、パチョリ6g。レンズ豆を350mlの水に入れて10分間煮沸します。次に、ポリア・ココス、オオバコ、パチョリを加え、100mlになるまで煮沸します。1日1回、3〜5日間連続して服用してください。 8. 慢性肝炎:ヤムイモ、ベルガモット、白レンズ豆を各50g、大麦麦芽を30g、白砂糖を適量。お粥を炊いて、食べるときに適量の砂糖を加えます。食欲不振、腹部膨満、下痢などの慢性肝疾患患者に適しています。 9. 脾臓を強化し、胃を養う:白豆と生姜各15g、ビワの葉、茯苓、高麗人参、枸杞子各0.3g、チガヤの根1g。上記の薬材を粗い粉末に挽き、水で煎じて残留物を取り除き、ビンロウの実粉末3gを加えて4回に分けて服用します。 10. 夏の暑さと湿気による赤痢、腹痛、しぶり腹:レンズ豆の花を15~18g、目玉焼きと一緒に食べます。 11. 急性胃腸炎、嘔吐、下痢:白レンズ豆を炒めて粉末状にします。1回12gを1日3~4回、温水で摂取してください。 12. 発熱、イライラ、喉の渇き、排尿困難を伴う熱中症:白レンズ豆を30~60g取り、スープとして煮て、冷めたら2回に分けて飲みます。 13. 乳児の栄養失調:白レンズ豆60g、鶏砂肝30g、黒ゴマ20g、もち米20gを別々に炒めて焦げ目がつくまですりつぶし、1回につき5gずつ摂取し、砂糖と塩水を加えてペースト状にし、1日2~3回摂取します。 14. 熱中症:緑豆100g、大豆と白レンズ豆各30g。 3種類の豆を水で柔らかくなるまで煮て、濃縮した汁に砂糖などの調味料を加えて飲みます。 15. 白帯下、下痢:白米豆100g、白レンズ豆50g、ヤムイモ50g、白砂糖50gをお粥状に煮ます。 16. 口腔カンジダ症:ローズマリー6g、生姜2片、白レンズ豆6gを水で煎じて、1日1~2回摂取します。 17. 不眠症:ゴルゴンフルーツ、ハトムギ、白レンズ豆、蓮の実、ヤムイモ、ナツメ、リュウガン、ユリ各6g、米150g。まずハーブを40分間煮て、次に米を加えてお粥になるまで調理を続けます。糖分を調整しながら数回に分けて食べ、数日間続けてください。 18. 高血圧:サンザシ30g、白レンズ豆30g、ブラウンシュガー50g。サンザシとレンズ豆をカリカリになるまで一緒に煮込み、黒砂糖を加えて食べます。 1日1回、3〜4週間服用してください。 19. 赤痢トウキ15g、ツルニンジン12g、オウゴンソウ9g、白レンズ豆12g、ヤマノイモ12g、ハトムギ11gを水で煮て服用してください。 1日1回。 20. 寒い:エルショルツィア・シリアタ 10g、マグノリア・オフィシナリス 5g、白レンズ豆 5g。エルショルツィア・シリアタとマグノリア・オフィシナリスを細かく刻み、白レンズ豆を黄色になるまで炒めてつぶします。魔法瓶カップに入れて沸騰したお湯で淹れ、しっかりと蓋をして、60分間温水に浸します。 21. 先天性心疾患。茹でた白レンズ豆150gの皮をむき、生の天日干し高麗人参粉末3gと白米150gを加えてお粥状にし、定期的に食べます。 22. 血小板減少性紫斑病。レンズ豆100gとナツメヤシ20個を洗い、鍋に入れ、氷砂糖50gと適量の水を加え、弱火で2時間煮ます。 1日2回、おやつとしてお召し上がりください。 |
推薦する
ヨーグルト栄養ご飯の作り方と効能
ヨーグルトとご飯は皆さんよく食べると思いますが、一緒に食べたことはありますか?ヨーグルトとご飯を混ぜ...
パンプキンパイの作り方
パンプキンパイといえば、誰もが柔らかくて甘い感じを思い浮かべるでしょう。パンプキンパイの作り方をご紹...
リン酸二水素カリウムを使用すべきでない花 (リン酸二水素カリウムを使用すべきでない花)
植物が繁茂するには、花の肥料は触媒のようなものです。適切に施用すれば、継続的に肥料を供給して植物をよ...
竹茸を使った鶏の腰煮の手順
竹茸煮鶏もも肉を食べたことがある人は多いと思います。とても美味しいですよ。私はよく家で自分で作って、...
温室で椎茸を育てる方法
椎茸は、特に栄養価の高い菌類の一種で、さまざまなビタミンやミネラルが含まれているだけでなく、体の病気...
煮たサトウキビ水を飲むとどんな効果があるのでしょうか?サトウキビ水を煮るコツ
サトウキビはそのまま食べるだけでなく、お湯を沸かして飲むこともできると聞いたことがある人もいるでしょ...
玄関前に桑の木を植えてもいいでしょうか?
玄関前に桑の木を植えてもいいでしょうか?玄関前に桑の木を植えるのは縁起が良くありません。これは、桑の...
醤油漬けピーマンの作り方
今日は、みんなで一緒に学べる家庭料理を用意しました。唐辛子の醤油漬けです。とても家庭的ですが、おいし...
小麦の牛肉粥
これからご紹介するのは、小麦穀粒牛肉粥についての知識です。気に入っていただければ幸いです。小麦の牛肉...
黒松の土壌交換時期と方法
黒松の土壌を変える時期黒松は毎年春に土替えをするのが一般的で、秋に行うこともできますが、春は2月下旬...
シソ油の役割と効能
シソ油は市場で人気の高級食用油で、シソ科の薬用植物シソの成熟した種子から抽出して搾った天然オイルです...
自宅でザクロを保存する方法
去年の秋、故郷に帰省した時、母がたくさんのザクロを持って帰ってきました。しかし、数日後、食べる前にザ...
千切りチキンヌードルの作り方と千切りチキンヌードルの栄養価
食欲をそそるチキンヌードルは、よく知られている冷麺料理です。栄養価が高く、スパイシーで香りがよく、鶏...
香りのよいつる植物にはどのくらいの頻度で水をあげればよいでしょうか?
香りのよいつる植物にはどのくらいの頻度で水をあげればよいでしょうか?最も生育が盛んな春と秋には、3~...
ジャスミンの挿し木方法
ジャスミンは気温が適切であれば一年中成長し、開花し続けます。枝の成長が比較的早いため、ジャスミンを栽...