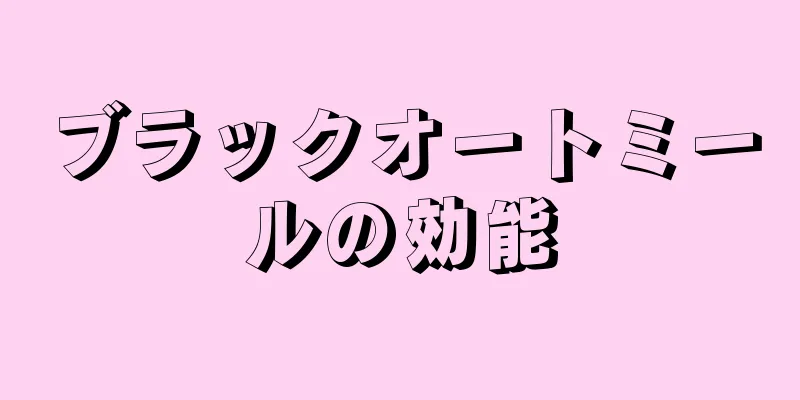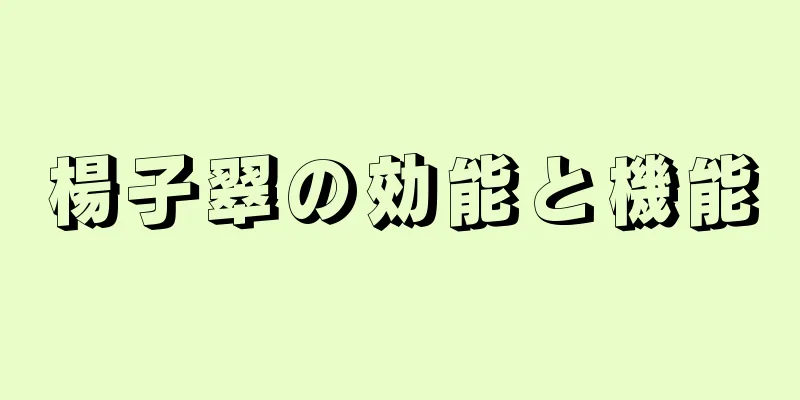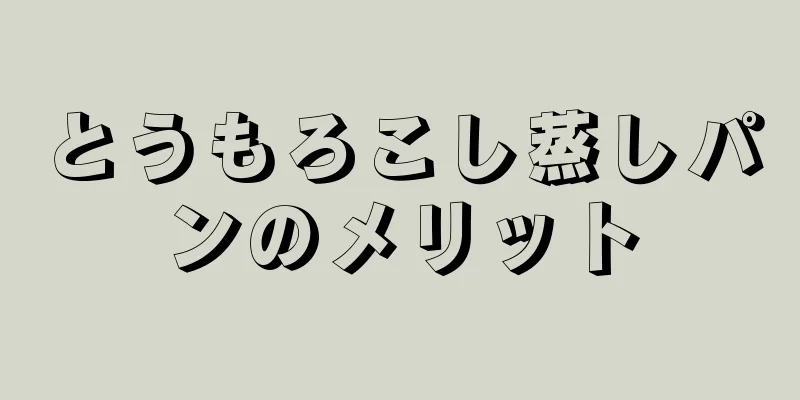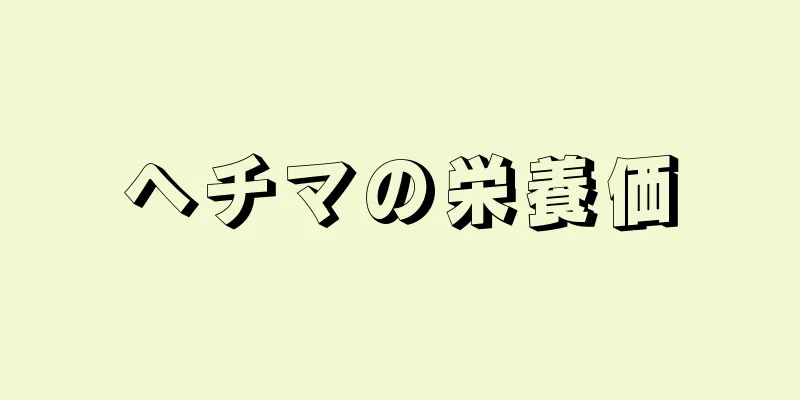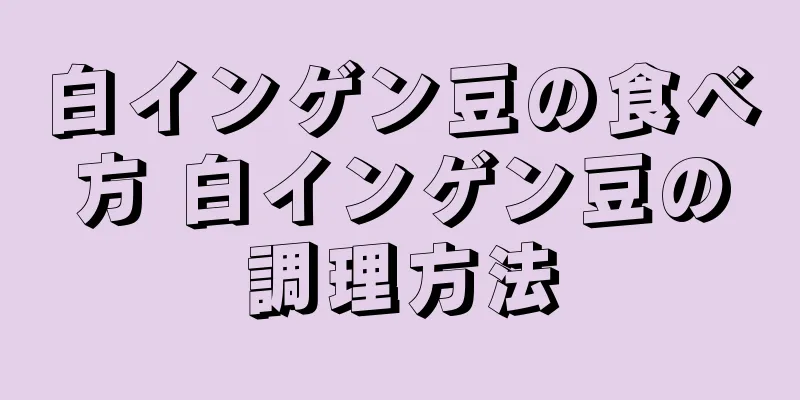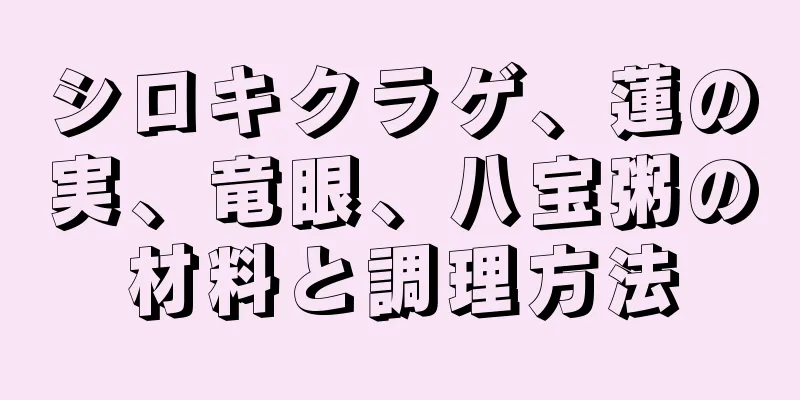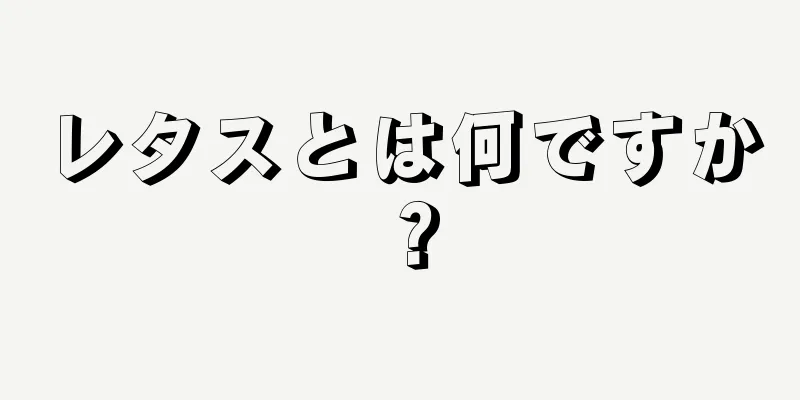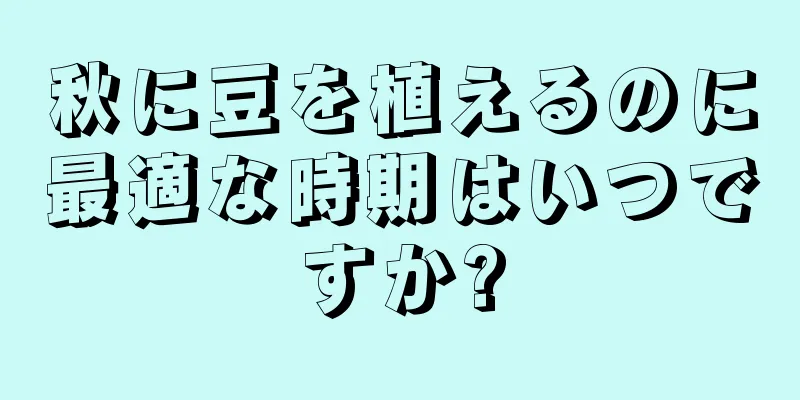トマトの花と実の落下とその予防と制御
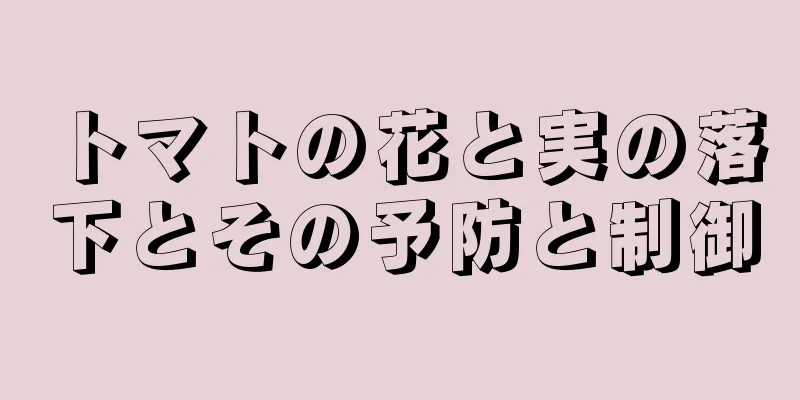
|
トマトの花や実が落ちると、収穫量に大きな影響が出ます。では、このような現象が起きてしまったらどうすればいいのでしょうか? 1. トマトの花と果実が落ちる理由1. 病害虫が花や果実の落下を引き起こします。トマトは植え付けから収穫まで、さまざまな病害虫の被害を受けます。1. ウイルス性疾患により、花芽が茶色くなり、その後落ちます。果実は変形したり腐ったりして、基本的に商品価値を失います。同時に、葉が丸まって色が変わり、光合成機能に影響を与え、花や果実の落下を引き起こすこともあります。通常の年では、落下率は20%~30%ですが、ひどい場合は70%以上に達することもあります。 ②灰色かび病は花芽を萎縮させる。 ③早期疫病により葉が茶色くなり、光合成機能が失われます。 ④ 炭疽病は果実に大きな茶色い斑点を引き起こし、それが果実の腐敗を引き起こします。 ⑤ 日焼けは直射日光により果皮が白くなり、病原菌の侵入を招き、果実を腐らせる原因となります。 6. 軟腐病により、果実は臭くなり、果汁が多めになり、皮だけが残ります。 7. コナジラミは茎や葉の汁を吸い、栄養分の枯渇や果実の斑点化を引き起こし、ウイルス性疾患も蔓延させます。オオタバコガ、アワノメイガ、その他の昆虫も果物に穴を開けて腐敗させる可能性があります。 2. 栄養不足は花や果実の落下を引き起こします。不適切な施肥は栄養成長と生殖成長のバランスを崩し、枝や葉が過剰に成長して植物に過大な負担がかかり、果実が実らないか、花や果実のほとんどが落ちてしまいます。管理が不十分で、枝の剪定を怠り、花や果実を適時に摘み取らないと、栄養分の損失を引き起こします。土地が不均一で、灌漑や大雨の後に表面に水が溜まると、根の呼吸が悪くなり、養分の吸収が妨げられます。軽度の場合は花や実が落ち、重度の場合は植物全体が枯れてしまいます。 3. 過酷な環境は花や果実の落下を引き起こし、高温と干ばつは植物の老化を促進します。早期老化と同時にウイルス性疾患を引き起こし、花や果実が落ちる原因となります。雨や曇りが続くと、植物の光合成機能が低下し、肥料不足で黄色くなり、病気の蔓延、根腐れ、苗の枯死、花や果実の黄変や落果につながります。強風、大雨、雹によって花や果実が落ちることもあります。 2. トマトの花や実が落ちないようにするには1. 強い苗を栽培する。強い苗は移植後の生存率とストレス耐性を向上させることができます。ストレス耐性の強い品種を選択することが前提条件です。現在、新しい耐病性および高収量品種には、主に中紅1号、茅紅、台湾紅、李勝シリーズなどがあります。栄養土の準備は合理的でなければなりません。その割合は、肥沃な庭土と完全に分解された馬糞がそれぞれ 40%、古いスラグが 20% です。混合後、1 立方メートルあたり 1000 〜 1500 グラムの硝酸とリンを追加し、よくかき混ぜれば準備完了です。種子処理は、まず種子を水に浸し、その後温度を変えて発芽させてから播種することで、苗の耐寒性とストレス耐性を向上させることができます。苗木の根系が確実に発達するように、殺虫剤や殺菌剤は下層土に混ぜるのではなく、覆土に混ぜる必要があります。苗の段階では、苗が活発に光合成を行えるよう、温度と湿度を管理して十分な光時間を確保する必要があります。苗床表面の湿度が高い場合は、成長を促すために苗を引き抜き、木灰を散布すると、湿度を下げて茎を強くするのに役立ちます。強い苗の基準は、節間が短く、葉が厚く、茎が強く、植物全体が濃い緑色で、手で軽く押すとすぐに跳ね返ることです。 苗に本葉が3~4枚になったら株分けして移植し、根毛の成長を促します。植物が1エーカーあたり生存してから、約7日かかります。植えることもできます。この方法で栽培された苗木は、病気の問題が少なく、弱い苗木が少なく、逆境に対する抵抗力が強くなり、植え付け後の生存率が13%以上向上します。 2. 科学的管理:灌漑可能で排水の良い中性ローム土を選択し、3年以上の輪作を実施します。畝立てとフィルム被覆により、栄養を調節し、土壌の温度と湿度を保護します。その後、フィルムは光を反射し、果実の着色を促進します。 ①施肥は「三本柱、三投入」を基本とし、元肥を主として追肥で補う;有機肥料を主として化学肥料で補う;根元施肥を主として葉面散布で補う。肥料には窒素が必要であり、 リンとカリウムは組み合わせて施用し、より多くのリンとカリウム肥料を施用する必要があります。これらは有機肥料と混合して事前に発酵させ、干ばつ時に有機肥料に浸透して養分の損失を減らす必要があります。 ② フィルムで覆われた畝の両側に苗木を植え、一般的には1ムーあたり約4,000本の苗木を残します。苗の段階では、養分の消耗を避けるために、適切な剪定を行い、側枝を適時に除去する必要があります。 ③ 中期および後期の管理では、「三適」措置を講じるべきである:適時に強い光を遮断する(果実を草で覆う)、適時に温度を調整する(昼間は30℃を超えず、夜間は15℃を下回らない)、正午の気温が高い場合は葉に水をかけて冷却する、適時に耕起、土寄せ、倒伏防止を行う。 ④ 水やりの注意点3つ:地面が乾いたらすぐに水を与える、大量の水をかけずに少量ずつこまめに水を与える、溜まった水は適時に排水する。 ⑤ 植物の高さが約25cmになったら、結実後にラックを挿入して植物を縛り、果実が地面で腐敗するのを防ぎ、畑の風通しと光環境を改善して果実の熟成を促進します。 ⑤ 花と果実を適度に保ち、弱った花と果実を適時に除去し、結実後の灌水時に人糞尿を散布し、その後は耕作を行わず、植物の早期老化と果実落下を防ぎます。 5~6 束の果実が成長した後、大きくて良い果実の数を増やすために、上部を摘み取り、下部の古くて黄色い葉を適時に取り除く必要があります。 3. 害虫防除は予防が主な方法です。検査を強化し、タイムリーで的を絞った予防と防除を実施します。①ウイルス性疾患の予防と防除には、種子を10%リン酸三ナトリウムに15分間浸し、きれいな水で3回洗浄して発芽を殺し、種子内のウイルスを除去します。最初の期間に2〜3回スプレーします。 予防には1000倍のNS-83阻害剤が使用されました。病気の初期段階では、ウイルスAを300〜500倍散布し、7〜10日後にもう一度散布し、2〜3回散布します。この期間中、葉面散布剤または0.1%〜0.2%リン酸二水素カリウムを2〜3回散布してウイルスを治療し、栄養を補給して植物自身の病気抵抗力を高めることができます。 ②炭疽病、灰色かび病、早期疫病などの真菌性疾患の予防と防除には、800~1000倍に希釈したメタラキシルまたは400~500倍に希釈したミョウバンを散布し、7~10日に1回散布し、合計2~3回散布して病気の蔓延を防ぐのがよい。 ③軟腐病などの細菌性疾患には、ストレプトマイシン100~150ml/kgを7~10日に1回、2回程度果実表面に散布すれば十分です。 4. 日焼けを防ぐために、果実の表面を草で覆うこともできます。 ⑤コナジラミの予防・駆除にはイミダクロプリドまたは3000~4000倍に希釈したスプレーをご使用ください。 ⑤ ワタボウフウやアワノメイガなどの穿孔性害虫には、卵発生ピーク時にワタボウフウまたは1000倍希釈のシペルメトリン、または2000倍希釈のシペルメトリンを散布します。7~10日ごとに3回散布します。害虫を駆除するために、2~3回殺虫剤を散布します。 4. 病気の感染を防ぐために、果物は熟した時に収穫します。同時に、病気の果物、腐った果物、虫のついた果物を取り除き、果樹園から運び出して深いところに埋め、人への感染を防ぎます。果実を収穫した後は、植物の成長に合わせて適時に肥料と水を与え、早期老化を防ぎ、未熟な花や果実への栄養の供給を促進し、その後の果実の収量と品質を確保する必要があります。 |
推薦する
ミルクメロンの食べ方は?栄養価はどれくらいですか?
ミルクメロンの食べ方は?栄養価はどれくらいですか?以下でこれらの質問に一つずつお答えしますので、ご参...
ネギ根の効能と禁忌
ネギは誰もが食べたことがあるはずです。日常生活でとてもよく使われる緑の葉野菜です。炒め物にしたり、詰...
アスパラガスシダにコカコーラで水やりできますか?コカコーラでアスパラガスシダに水をやる正しい方法
アスパラガスシダにコーラで水をあげても大丈夫ですか?アスパラガスシダはコーラで水やりできますが、その...
フィッシュボーンクレマチスの栽培方法と注意点
フィッシュボーンユリは比較的育てやすい植物です。成長過程であまり多くの水を必要とせず、砂漠でもよく育...
フリージアの球根発芽方法における3つの一般的な球根増殖技術
フリージアの球根を植える前に、まず発芽させます。これにより、フリージアの球根の生存率が上がり、発芽速...
黒ゴマ粥の効能
黒ゴマ粥の効能についてどれくらいご存知ですか?以下に詳しく紹介させていただきます。黒ゴマ粥黒ゴマは、...
インゲンは年に何回植えることができますか?一年中植えられますか?
インゲンは年に2回植えることができます。インゲンを植えるのに最適な時期は3月から4月の春ですが、イン...
バジルは日陰と太陽のどちらを好みますか?
バジルは日陰と太陽のどちらを好みますか?バジルは太陽を好む植物で、私の国では広く栽培されています。暖...
どの種類のキンモクセイが鉢植えに適していますか(どの種類のキンモクセイが家庭の鉢植えに最適で、最も香りが良いですか)
キンモクセイは伝統的な四大名花の一つです。長江の中流域と下流域のいたるところで見ることができます。公...
ココナッツミルクの効能と機能、そしてココナッツミルク摂取のタブー
海南省ではココナッツはどこでも見つかる果物だが、中国本土の住民にとっては比較的珍しいものだ。しかし、...
オレンジを食べることのメリットとデメリット
オレンジを食べるのが好きな人はたくさんいます。オレンジは肺をきれいにし、脾臓と胃を強くし、消化を促進...
レタスを植えるのに適した季節はいつですか?種まきに最適な月は何月ですか?
レタスを栽培するための条件はそれほど高くありません。一般的に4度以上の温度で植えられ、すぐに発芽しま...
ヘチマと海藻スープの効果は?ヘチマと海藻スープの栄養価
ヘチマと海藻のスープは、夏に最もよく飲まれるスープです。美味しくて栄養価が高いだけでなく、熱を取り除...
シミを薄くする食べ物は何ですか? シミを最も早く薄くする食べ物は何ですか?
気血不足や内分泌障害がある場合、または体内の毒素が時間内に代謝できない場合、皮膚表面に斑点が現れます...
みかんが実を結ぶには何年かかりますか?
みかんの栽培入門温州ミカンの主な生産地は広西、広東、浙江などです。この果実は扁平で甘く、糖分が多い。...